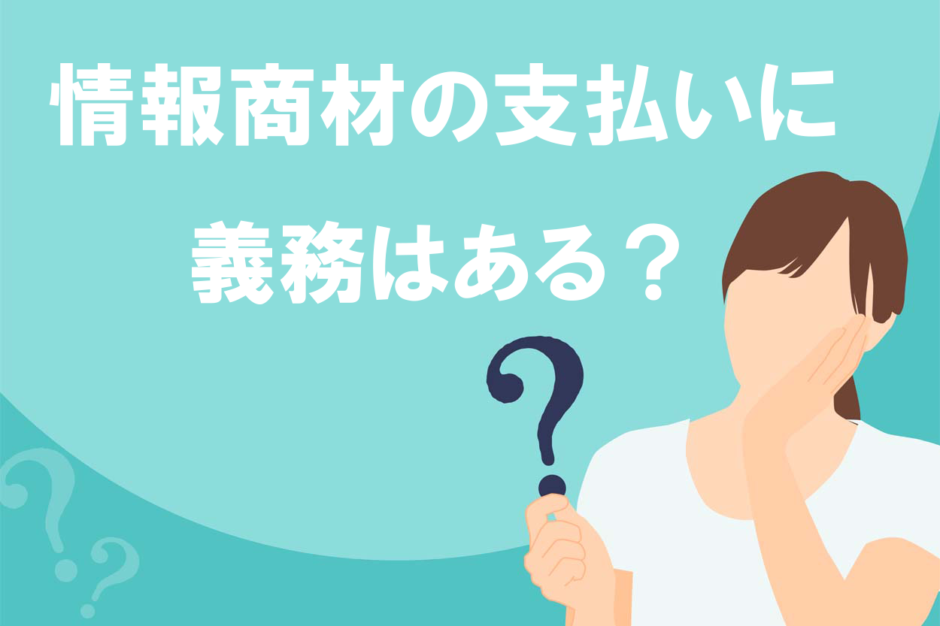副業ビジネスやSNSフォロワーの伸ばし方など、幅広いジャンルで販売されている情報商材。
優良なものはたくさんありますが、中には詐欺同然の商材も多く見受けられます。
そこで「内容が詐欺に近いものでも、支払いの義務はあるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?
内容が不満だと感じるものだったら、支払いの処理を進めたくないですよね。
実は情報商材には、原則として支払い義務が存在します。
ただし内容によっては、支払いを拒否することが可能です。
この記事では支払い義務のない情報商材の特徴や、支払いを無効にするためのポイントについて解説します。
返金に強い相談先についても紹介するので、情報商材の購入代金を支払いたくないと考えている方は、ぜひ記事をご覧ください。
情報商材には原則として支払い義務が発生する

情報商材を購入した場合は原則、支払い義務が発生します。
商品を購入すると「売買契約」が成立します。消費者はその契約に基づいて、代金を支払う義務が発生するのです。
特にインターネットで購入した場合「自ら商品の決済ページに進んだ」と解釈されます。
つまり自発的に商品を購入したことになるので、内容が不満であっても代金を支払わなくてはなりません。
契約が成立している以上は、自己都合での支払い拒否はできないものだと考えておきましょう。
ただし、購入した情報商材が説明を受けていたものと違ったり、値段と見合わないものであったりと、詐欺に近い場合は返金を受けられる可能性があります。
支払の義務がない情報商材の特徴5選
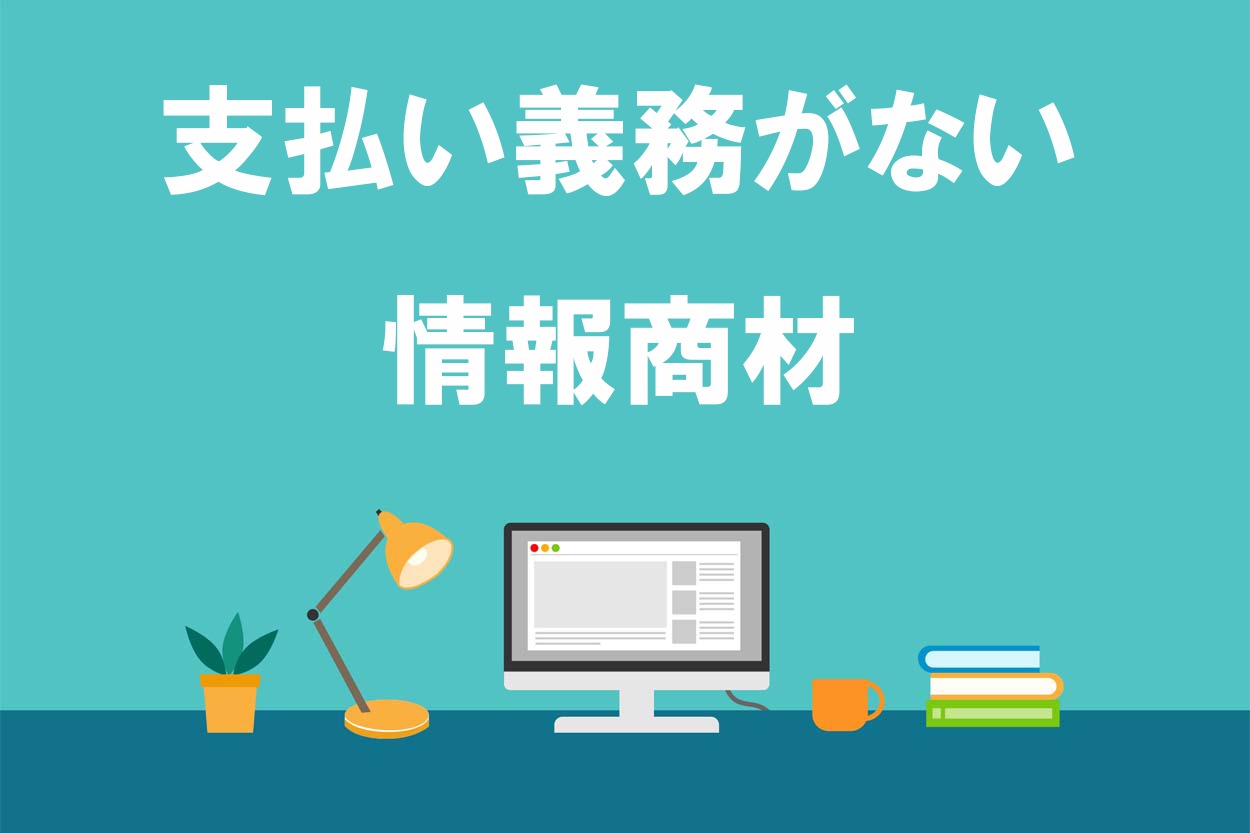
こちらでは、支払い義務がない情報商材の特徴について、以下の5つを解説します。
- 中身が聞いていたものと違う
- 他のコンテンツの丸パクリ
- 誇大広告
- 返金保証に応じない
- ずっと「◯日だけの限定」と売られている
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.中身が聞いていたものと違う
支払の義務がない情報商材の特徴に、事前のやり取りや説明で聞いていたものと、情報商材の中身が異なることが挙げられます。
この場合は「違う商品が届いた」という解釈になるため、支払いの拒否が可能です。
- 「1日5分で大金を稼げる」と書かれていたのに、全く稼げない
- 購入したソフトウェアを使っても儲けが出ない
- 無期限サポートと言われていたのに、返信が来ない
などのケースだと、支払いを拒否できる可能性が高まります。
事前の情報と、実際の商品の中身が大きく違う場合は、支払いの義務が無くなると考えておきましょう。
2.他のコンテンツの丸パクリ
情報商材のコンテンツが他の商品の丸パクリである場合も、支払い義務がないケースの特徴の1つです。
詐欺罪や特定商取引法違反のみに留まらず、著作権や知的財産権を侵害している可能性が極めて高いといえます。
身近な例だと、購入したブランド品が偽物だった場合は、支払いをしなくても問題ありません。
それと同じく、情報商材でも丸パクリなどの違法なものであれば、代金を支払う義務はないといえます。
3.誇大広告
誇大広告とは、商品やサービスの内容が「実際よりも良い」や「有利である」といったような消費者の誤解を招く広告のことです。
この場合は事実と異なると解釈されて、支払い義務がなくなる可能性が高まります。
- 確実に100万円稼げるビジネス
- 1日5分で確実に10万円手に入る副業
- 半年で資産が倍になる投資法
などの触れ込みがある広告を見て購入したものの、実際にまったく成果が出ないという場合は、支払いの義務はありません。
4.返金保証に応じない
「購入後に返金できます」と書いてあったにも関わらず、応じない場合は支払いの拒否が可能です。
契約違反に該当するため、そもそもの売買契約自体を無効にできます。
また「本当は返金に細かな条件があるにも関わらず、その説明が無かった」という場合でも、支払い義務はありません。
- 返金保証がある
- 100%元が取れる
- 儲かるまでサポートする
上記のような返金保証に関する文言があっても、お金が返ってこない場合は、代金を支払わなくても問題ありません。
5.ずっと「◯日だけの限定」と売られている
限定と書かれているにも関わらず、ずっと販売されている商品も、支払いの義務が発生しない可能性が高いです。
消費者に対して嘘の広告を流していると捉えられるため、契約違反だといえます。
- 3時間以内なら◯%オフ
- 今月中にお申し込みされた方に限り割引
- あと24時間で販売終了
などと書かれているにも関わらず、ずっと商品が販売されている際には、支払いが拒否できると考えて問題ありません。
情報商材の支払い義務を無効にするためのポイント4選
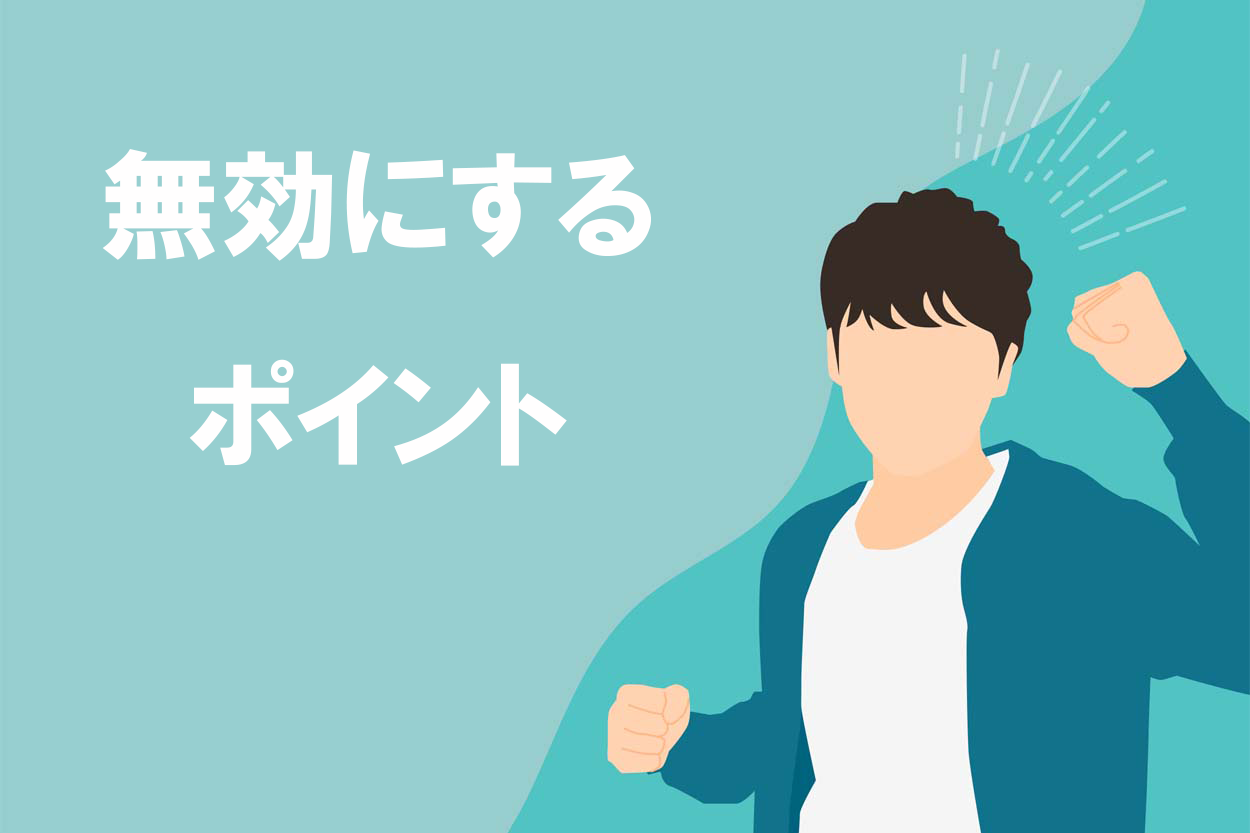
こちらでは、情報商材の支払い義務を無効にするためのポイントを紹介します。
- 契約違反の証拠を集める
- 販売業者の情報をまとめる
- 信頼できる機関に相談する
- クーリングオフが適用できるか確認する
支払い義務を無効にするためにも、それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.契約違反の証拠を集める
情報商材の支払い義務を無効にするために重要なのが、契約違反を立証するための証拠集めです。
詐欺や誇大広告など、契約や法令に抵触した取引であることを裏付けなければなりません。
- 情報商材の販売ページ
- メールマガジンやLINEメッセージ
- 担当者とのやりとり
など、明らかに契約と内容が違うということを証明できるように、スクリーンショットなどで証拠を集めておきましょう。
2.販売業者の情報をまとめる
販売業者の名前や住所・電話番号などの情報をまとめておきましょう。
基本情報が無いと、支払い義務を無効にするための行動を取れません。
仮にインターネットを介した売買の場合「特定商取引法に基づく表記」によって、販売業者の名前や連絡先を明記することが義務付けられています。
直接取引の場合でも、相手からもらった名刺や資料は保管し、情報をまとめておいてください。
3.信頼できる機関に相談する
弁護士や国民生活センターなど、信頼できる機関に相談しましょう。
特に弁護士であれば、詐欺の調査から刑事告訴まであらゆる訴訟業務を代行してくれます。
相談料や着手金が無料の事務所もあるため、ほぼ負担なしで話を進めることも可能です。
法律関係の話になると、個人ではなかなか対応できないことが多いため、弁護士などの解決する力がある機関に相談することは非常に効果的だといえます。
4.クーリングオフが適用できるか確認する
クーリングオフが適用できるかも確認しておきましょう。
クーリングオフとは、一定の条件かつ一定の期間内であることを満たせば、相手の合意なく契約を取り消せる制度のことです。
クーリングオフを適用できる場合は、消費者センターに相談しなくても返金につなげられるため、とても効果的の方法の1つといえます。
クーリングオフの適用条件は、以下のとおりです。
- 電話勧誘販売取引:8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
- 業務提供誘引販売取引:20日間
適用できる期間は限られていますが、確実に返金を受けられるため、使えるかどうかを確認してみてください。
情報商材の支払い義務を無効にするための相談先3選
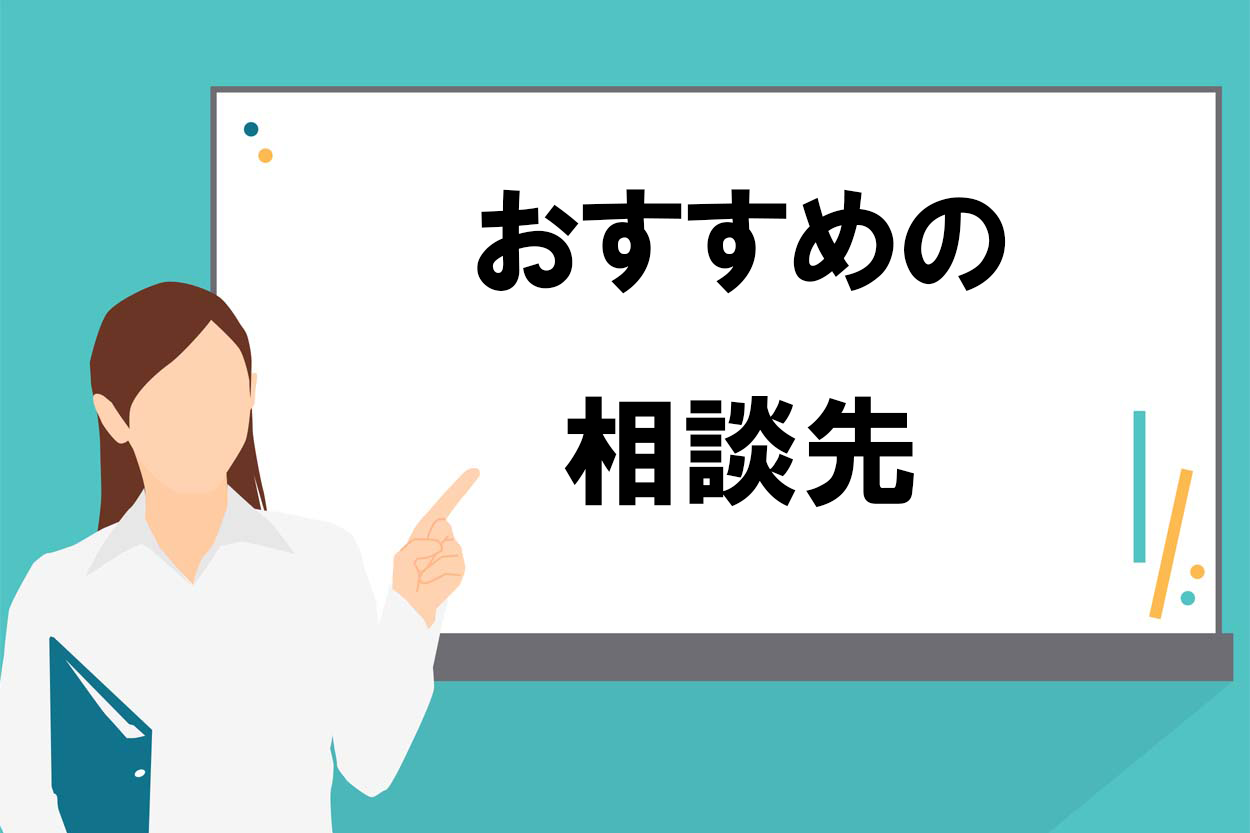
情報商材の支払い義務を無効にするための相談先を3つ選んで紹介します。
- 弁護士
- 国民生活センター
- クレジットカード会社
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.弁護士
弁護士は法律の知識を用いて、情報商材の契約無効を訴えられる最善の手段です。
証拠集めや業者への返金勧告など、個人だと手間がかかることをすべて一括で代行できます。
また弁護士に相談することで、刑事告訴や民事訴訟となった場合に、相手の合意がなくても裁判が可能です。
さらに判決で「返金しなければならない」と決定したにもかかわらず、販売業者が応じない場合でも、強制執行の手続きができます。
弁護士は情報商材の支払い義務や返金の相談する際に、非常に有効な相談先です。
2.国民生活センター
国民生活センターへ相談すると、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用して支払い義務を無効することが可能です。
ADRとは、情報商材を購入した人(消費者)と販売業者の間に国民生活センターが入り、仲介・仲裁して和解を手助けしてくれる制度です。
さらに国民生活センターには、以下の特徴があります。
- 安価な費用で済む可能性が高い
- 解決までの期間が短い
- 法的根拠を持って話ができる
ただしADRは相手の合意が無いと進められないため、業者に返金の意志がない場合は、弁護士に相談して裁判を起こすことが効果的です。
弁護士と国民生活センターの両方に相談を行うことで、相手がどのような対応をしてきても返金の交渉ができるようになります。
3.クレジットカード会社
情報商材の支払いをクレジットカードで行っていた場合、カード会社に問い合わせることで解決へとつながる可能性があります。
クレジットカード会社には「チャージバック制度」があり、クレジットカードの不正利用や悪用が認められると決済を取り消すことが可能です。
決済を取り消しできると確実にお金が返ってくるため、クレジットカードで支払った場合には、クレジットカード会社に一度、問い合わせてみましょう。
詐欺被害にあった方へ
LINEで無料相談受付中
LINEで無料相談受付中

「なんで騙されてしまったんだ」 「どうにかして返金できないか?」 とお悩みのことでしょう。 実は司法書士に任せると返金される可能性があると知っていましたか? LINEで無料相談できるので、一度返金できるかどうか確認してみてください。