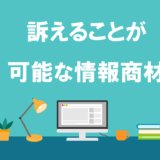「情報商材を購入したが詐欺だったかもしれない」
「返金をして欲しいがどう対応すればいいかわからない……」
「だれかに代行してもらいたいけど、どこに相談すればいい?」
などと考えていませんか?
情報商材は商品やサービスとしての枠組みが複雑で、返金して欲しくてもどうすればいいのかわからないかもしれません。
このような場合、自分1人で考え込むよりも専門の弁護士・司法書士に代行するほうがスムーズに進む可能性が高いです。
そこでこの記事では、情報商材の返金事例や、代行の方法について解説します!
情報商材を購入したが返金して欲しくて困っている、弁護士・司法書士を雇おうか検討している方は、ぜひ記事をご覧ください。
返金できる情報商材詐欺の事例3選
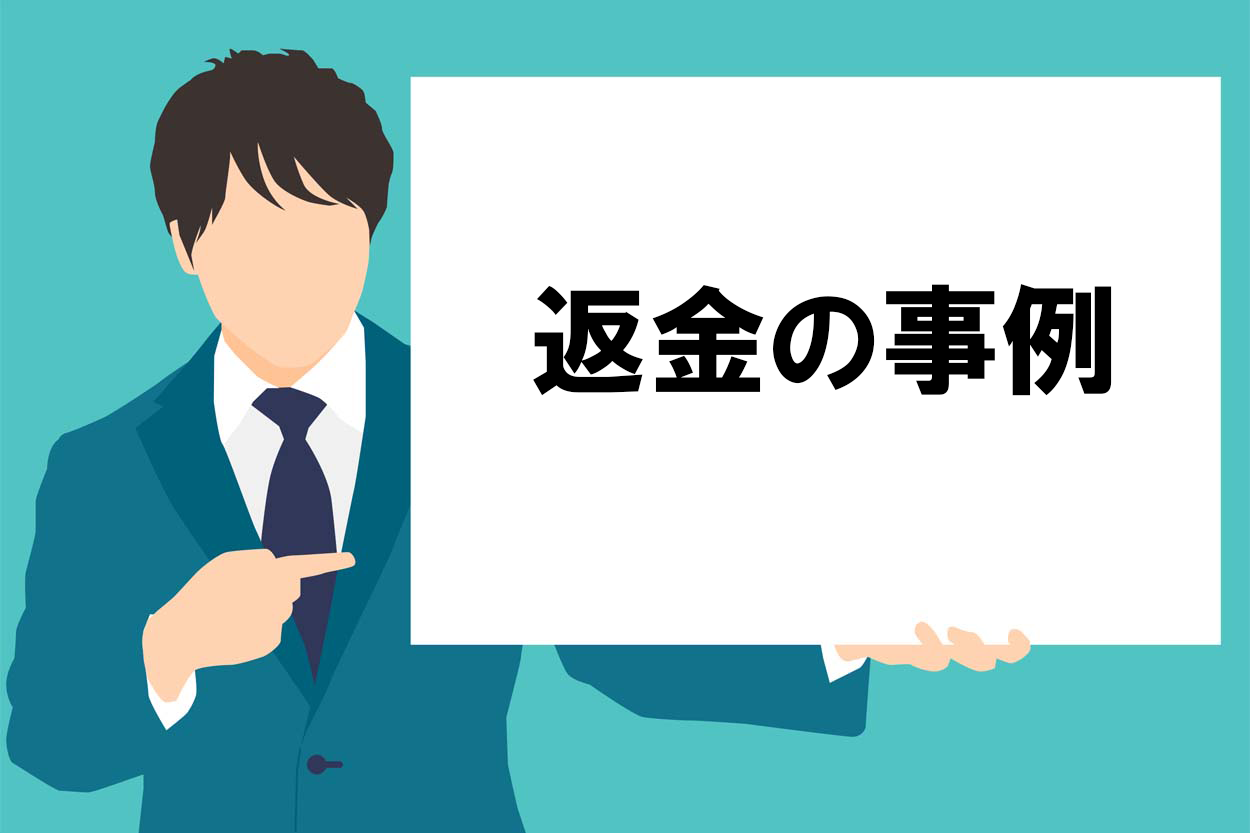
こちらでは返金できる情報商材の事例を3つ紹介します。
- 誇大広告が認められた
- カード会社から返金された
- ADRによる和解
それぞれ確認していきましょう。
1.誇大広告が認められた
1つ目が、誇大広告の違法性が認められることで、返金対応で可能になるケースです。
詐欺的な情報商材の販売を行っている業者のほとんどが、誇大広告と呼べるような過度な宣伝をしています。
- 「過去最大」「◯◯としては最高月収」などの誇張表現
- 「絶対に稼げる」という断定
- 最初の購入では価格を安く見せたが実際は違った
など、こういった過度な表現を用いて消費者を騙すような販売方法は、景表法で違法とされています。
弁護士・司法書士を通じて、販売方法そのものに違法性があったとして返金を要求することで、大事にしたくない業者側は返金を認めることがあります。
2.カード会社から返金された
情報商材をクレジットカードで支払っていた際に、情報商材業者が応じなくても直接連絡することで、すんなりと返金が完了することがあります。
クレジットカードには、不正使用時の請求を取り消す「チャージバック」という制度が備わっていることが多いです。
これはオレオレ詐欺や盗難時の対応策として用意されているものですが、情報商材にも利用できるケースがあります。
- 決済をしたが支払いの確定が決まっていない
- まだ引き落としが行われていない
- リボ払いや分割払いを利用している
という場合は、クレジットカードの取り消しができるかもしれません。
3.ADRによる和解
ADRとは消費者センターが行う、いわば「仲裁」です。
消費者と事業者(販売元)の間に入って、問題解消を手伝います。
消費者センター(国民生活センター)は全国に800箇所ある地方公共団体が設置する行政機関で、無料で相談が可能です。
仲裁合意書を作成し、事業者側と交渉、和解できれば返金につながります。
広告の表示の仕方や教材の不備などが見つかり、さらには証拠を提示できれば、和解が成立しやすくなる事例が多いでしょう。
情報商材の返金は難しい?泣き寝入りになる事例3選

こちらでは、情報商材の返金を試みたものの、結局泣き寝入りになってしまった事例を3つ紹介します。
- クーリングオフが適用できない
- 警察に相談しても解決に繋がらない
- 消費者センターが対応してくれない
それぞれ確認していきましょう。
1.クーリングオフが適用できない
クーリングオフ制度とは、商品やサービスの購入・契約をした後でも、何らかの不備によって撤回したい際に一定の期間内であれば無条件に利用できる制度です。
具体的には以下のような取引が対象となります。
- 訪問販売・訪問購入
- 電話勧誘による販売
- マルチ商法などの連鎖販売取引
- 業務提供誘引販売
このうち情報商材は、電話勧誘による販売や連鎖販売取引、業務提供誘引販売などに該当する可能性があります。
ただし、以下のような場合には、適用が難しい場合があります。
- 購入した情報商材がクーリングオフの対象にならない
- クーリングオフできる期間(8日~20日が過ぎてしまっている
- クーリングオフの通知書の送付先や販売元の連絡先そのものが不明
2.警察に相談しても解決に繋がらない
警察に被害届を提出することは、詐欺被害の対応手段の1つとして一般的です。
ところが警察への相談では、返金を受けられる可能性がかなり低くなっています。
仮に警察が犯人を逮捕したとしても、刑事事件では被害者への返金を強制できません。
被害者が返金を要求するには、あくまでも民事裁判が必要です。
業者が姿をくらましているときに、警察の力を使って身元を明かすことは可能かもしれませんが、返金にまで結び付けられることはほとんど無いと考えておきましょう。
3.消費者センターが対応してくれない
消費者センターに電話をすると、様々なトラブルの相談に乗ってくれます。
ただしあくまでも「相談」であって、消費者センター自体は返金への強制力を持っていません。
状況によっては相手の業者に注意勧告をしたり、ADRによる和解交渉が可能ですが、相手が応じない場合は返金につながらないことも十分にありえます。
個人では行いにくい調査をしてくれる場合もあるので、必ずしも役に立たないわけではありませんが、返金代行までは頼めないことが大半です。
情報商材の返金代行を依頼できるのは弁護士・司法書士のみ!3つの手段を紹介
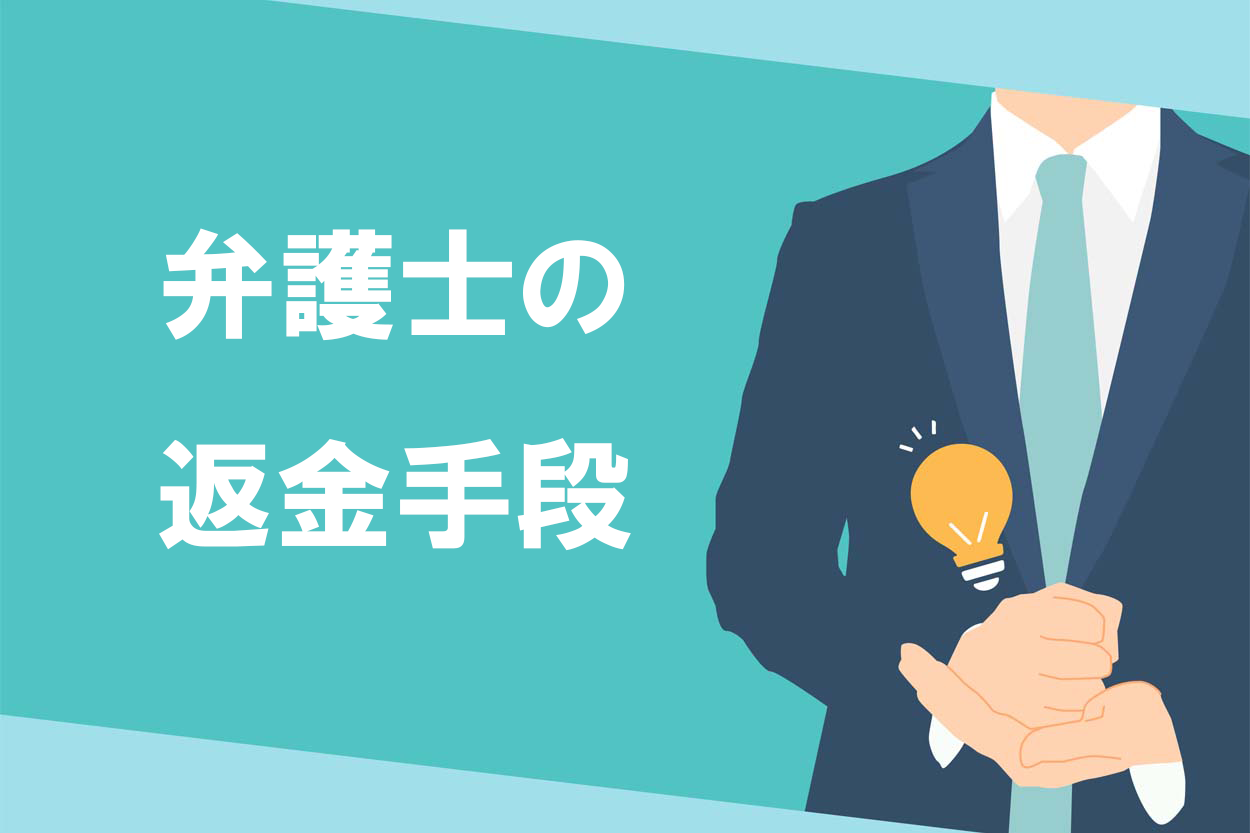
個人が利用できる返金代行の依頼先は、弁護士・司法書士のみです。
弁護士・司法書士であれば、事業者の個人情報の開示や特定、返金の要請を行えます。
こちらでは、弁護士・司法書士に返金代行を依頼した場合に使える3つの手段について紹介します。
- 販売元に返金要求
- クレジットカード会社に申し立て
- 民事訴訟や刑事告訴
ぜひ参考にしてみてください。
1.販売元に返金要求
弁護士・司法書士を通せば、販売元である事業者に直接、返金要求ができます。
被害者の代行という形で、法的な根拠に基づいて返金請求を行うため、非常に効果が高いです。
さらに民事訴訟を起こすことも可能なので、詐欺で失ったお金を取り返せる確率が大きく高まります。
個人で要求しても業者から相手にされない可能性が高いですが、法律のプロである弁護士・司法書士であれば返金に導けることもあるでしょう。
2.クレジットカード会社に申し立て
情報商材の購入にクレジットカードを利用している場合は、弁護士・司法書士から取り消しの申し立てを行えます。
クレジットカード会社の決済そのものを取り消してしまえば、業者にお金が行くことはありません。
この制度は「チャージバック」といい、オレオレ詐欺や不正利用などの対応策として用いられます。
カード決済が完了していても割賦販売法が適用できれば、返金手続きが可能です。
高額な商材をクレジットカードで決済している場合は、弁護士・司法書士に申し立てを依頼してみましょう。
3.民事訴訟や刑事告訴
詐欺に悪質性が高かった場合には、民事訴訟や刑事告訴を求めることもできます。
民事訴訟で勝訴すれば、法的な強制力が得られるため、返金を受け取ることが可能です。
また訴訟をちらつかせることによって、相手が示談を求めてくることもあります。
訴訟は個人でも可能ではありますが、法的な知識や書類の準備が必要なので、あまりひとりで進めても効果がありません。
そのため弁護士・司法書士に依頼して、代行という形で訴訟を進めたほうが、解決までの時短につながります。
【無料相談可】情報商材の返金に強い弁護士・司法書士
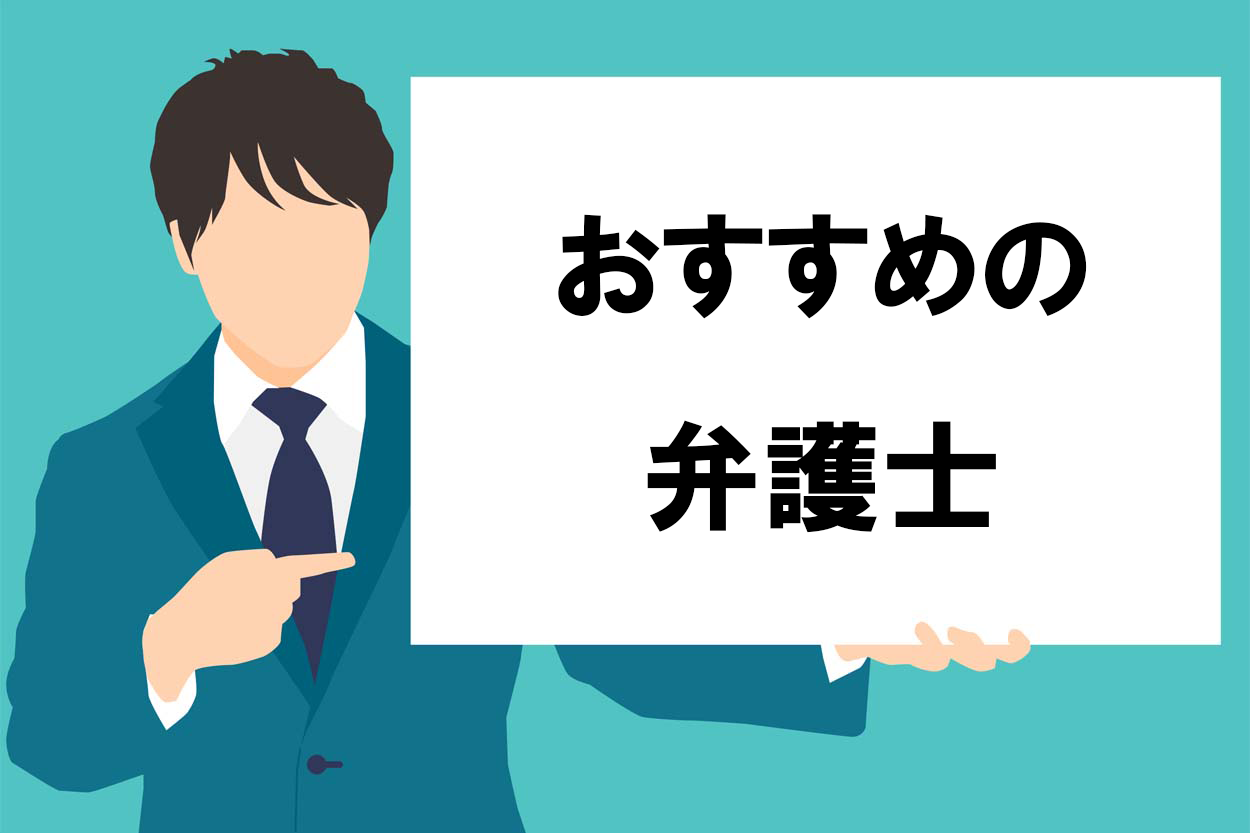
こちらでは、情報商材の返金に強い法律事務所を紹介します。
丹誠司法書士法人
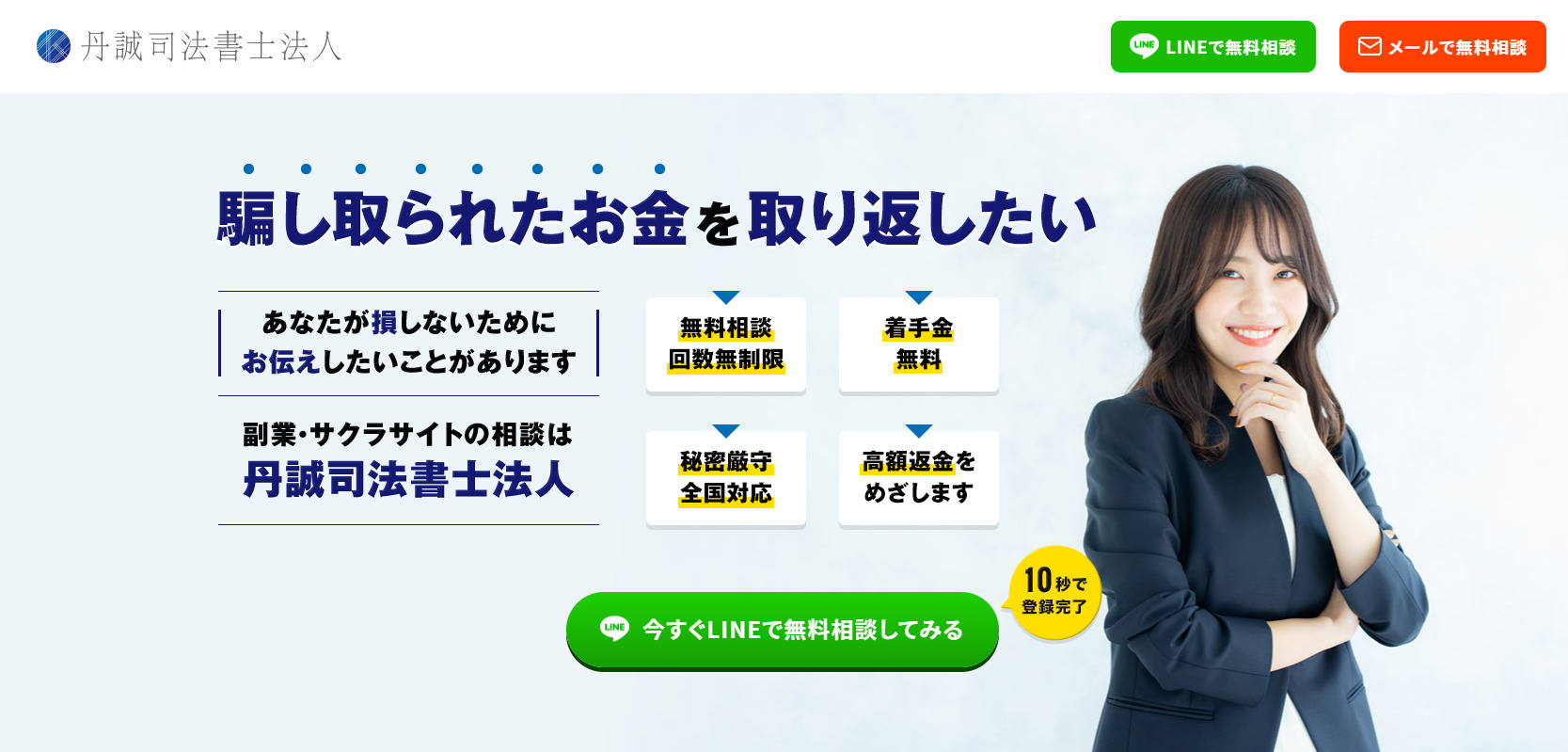
| 住所 | 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア5階 |
| 相談方法 | ・電話 ・メール ・LINE |
| 相談時間 | 電話:9:00~19:00 メール・LINE:24時間 ※土日祝も受付 |
| 対応エリア | 全国 |
| 備考 | 相談・着手金無料 |
丹誠司法書士法人
は、インターネット上の副業詐欺・サクラサイト詐欺に対応している司法書士事務所です。
無料相談可能&後払いの完全成功報酬制をとっているため、最初に追加でお金を支払う必要はありません。相談は何度でも行えるため、悩みや不安点を解消したあとに依頼することが可能です。
短いサイクルで会社名や連絡先を変更する詐欺業者に対応できるように、専任スタッフによるスピーディーな対応を心がけています。さらに全国対応しており、どの地域からでも相談できる点も魅力です。
メールやLINEでは24時間対応しているので、まずは無料で問い合わせを行ってみてください。
詐欺被害にあった方へ
LINEで無料相談受付中
LINEで無料相談受付中

「なんで騙されてしまったんだ」 「どうにかして返金できないか?」 とお悩みのことでしょう。 実は司法書士に任せると返金される可能性があると知っていましたか? LINEで無料相談できるので、一度返金できるかどうか確認してみてください。
-940x626.png)
-160x160.png)