インターネットを活用した「副業」や「お金を稼ぐためのノウハウ」などを謳った情報商材が多く出回っています。
ところが詐欺まがいの商品が多く、高額なお金を出したものの内容がいまいちで「支払いを拒否したい」と考えている方も多いのではないでしょうか?
すでに支払ってしまったり、クレジットカードで決済をしてしまった場合、取り消して返金を受けられるのかは気になるポイントですよね。
そこでこの記事では、情報商材の支払いが拒否できるのか、拒否できる商品の特徴などについて解説します!
うっかり購入してしまった商材を返金したいと考えている方は、ぜひ記事をご覧ください。
情報商材の支払いは原則拒否できない
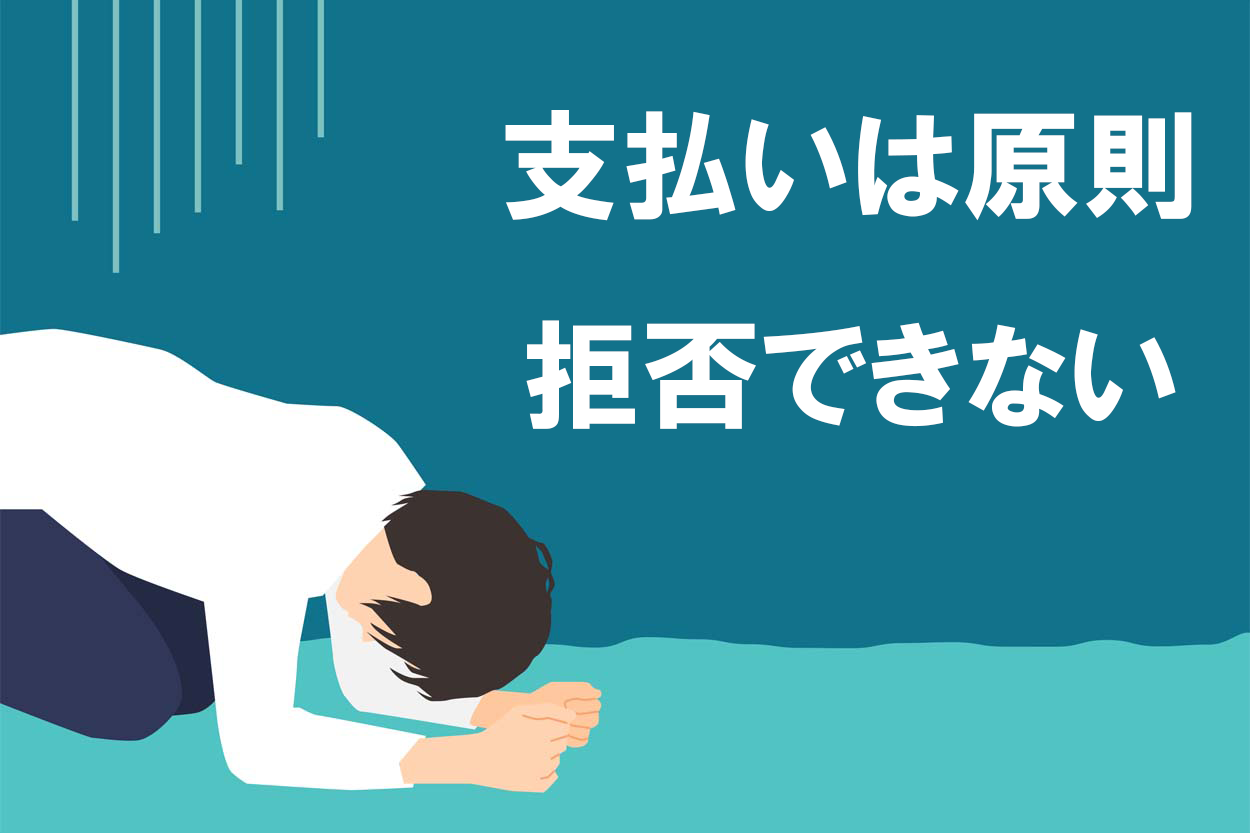
非常に残念ではありますが、情報商材を購入した場合、基本的には支払いの拒否はできません。
売買契約が成立している時点で、お互いに納得しているという状況が成り立ってしまいます。
特にインターネットで購入した商品の場合は、自分の意志で決済ページへアクセスしていると捉えられます。
そのため、商材の中身が自分にとってどんなに問題のある内容であったとしても、購入者には完全な支払いの義務が生じるのです。
ただし詐欺行為など、消費者が明らかに不利な状況にある場合は、支払いを拒否できることもあります。
支払ったお金を取り返すには、購入した際の状況を思い出して、柔軟に対応することが肝心です。
情報商材が詐欺だと支払い拒否できる可能性あり!5つの特徴を解説

すでに代金を支払っていたとしても、購入した情報商材に詐欺行為がある場合は、支払いを拒否できる可能性があります。
こちらでは、支払いを拒否できる可能性のある情報商材の特徴を5つ紹介します。
- 「必ず儲かる」などの誇大広告がある
- 商材の中身が聞いていた内容と違う
- 他人のコンテンツの模倣
- 「◯日だけの限定」といいつつ、引き続き売られている
- 返金保証があるのに応じない
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.「必ず儲かる」などの誇大広告がある
情報商材の説明文やメールマガジンなどで「誇大広告」が確認できた場合、支払いを拒否できる可能性があります。
- スマホを少しいじるだけで確実に◯◯万円稼げる
- 誰でも簡単に必ず稼げる
- この教材を買えば確実に短期間で儲かる
など、明らかに実現不可能な文言を使っている場合は、拒否を検討してみてください。
2.商材の中身が聞いていた内容と違う
いざ商材を購入し確認してみると、広告文や説明文と、実際の中身が違うというケースもあります。
この場合は事実誤認にあたるため、購入者は支払いを拒否できます。
たとえば「永年サポートに対応」とう内容をアピールしていたのに、いざ購入すると連絡が取れなくなったなどのケースです。
ショップページの内容と購入した商品を見比べて、あまりにも違いが大きい場合は取り消しの申請を行いましょう。
3.他人のコンテンツの模倣
情報商材の中身が「他人のコンテンツの丸パクリ」という事案も、支払い拒否ができる可能性があります。
- 他の教材をコピーしているだけ
- 海外の本を語尾を変えただけで転用している
などです。
これらは著作権法の違反にあたるため、知らずに購入した人は支払い拒否を申請してみてください。
「インターネットで商材と同じ文章を見つけた」という場合は、泣き寝入りせずに販売業者や弁護士に問い合わせしてみましょう。
4.「◯日だけの限定」といいつつ、引き続き売られている
情報商材の売り方として、限定商品感を出して焦りを引き出し、購入を促すというケースがあります。
この売り方が嘘だった場合、返金を受けられる可能性があります。
- 限定◯個・◯日といいつつ売られている
- 商品ページにタイマーがあるものの、毎回リセットされる
- 期間限定セールがずっと続いている
などの状況は、詐欺行為として考えられます。
期間限定と聞いて購入した商品がある場合は、返金できるかどうか検討してみてください。
5.返金保証があるのに応じない
情報商材に「成果がでなかった場合は全額返金」という文字があるのにも関わらず、実際には返金に応じてくれないというケースも存在します。
返金を要求しても「商材のとおりに行動しなかった」などの理由をつけて、返金を受けてくれません。
さらに悪質だと「効果が出なかった人のために、確実に成果が見込めるコースがある」と言って、さらに高額な商材を販売してくる場合もあります。
また購入した人も「使いこなせなかった自分が悪い」と思い込みやすく、泣き寝入りの可能性が高い手法です。
実際には、正当な理由なく返金保証に応じないのは詐欺行為にあたるため、支払いの拒否を申し出ることで、契約を取り消せる可能性があります。
支払い拒否を成功させるためのポイントを3つ紹介
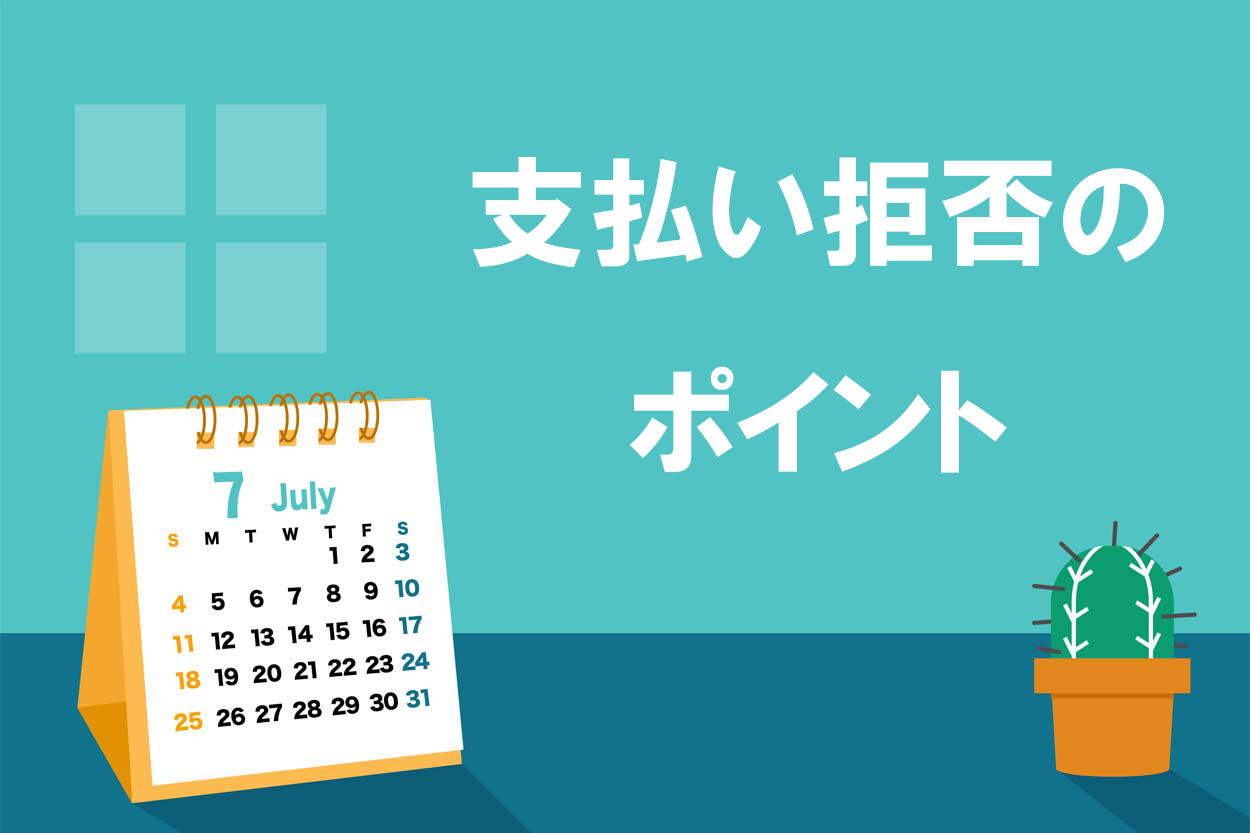
情報商材の支払い拒否は、販売された当時の状況によっては可能です。
そこでこちらでは、支払い拒否を成功させるためのポイントについて紹介します。
- 販売業者の情報をしっかり集める
- 詐欺の証拠を整理する
- 担当者とのやりとりを記録する
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.販売業者の情報をしっかり集める
交渉を行うためにも、まずは販売業者の情報を正確に集めていきましょう。
相手の情報がわからないままだと、雲隠れされてしまう可能性が高まってしまいます。
- 業者名
- 担当者の氏名
- 所在地
- 電話番号
などがあると効果的です。
インターネットで購入した場合は「特定商取引に基づく表記」として、連絡先を明記する必要があるため、ホームページから連絡先などを確認しておきましょう。
しっかりと控えでおくことで、後々の処理の流れをスムーズにできます。
2.詐欺の証拠を整理する
支払い拒否を行うために、詐欺の証拠を整理します。
商材のどの部分が詐欺に当たるのかを確認しておくことで、手続きをスムーズに進めることも可能です。
仮に民事裁判などにもつれ込んだ場合にも、強い武器として硬貨を発揮します。
- 商品の広告文
- メールマガジンの内容
- 実際の商品との違い
など、証拠は集められるだけ集めてください。
3.担当者とのやりとりを記録する
広告文だけでなく、担当者とのやり取りを記録することも大切です。
商品の販売方法によっては、担当者と直接会って話したり、メールでやり取りしたりして、勧誘を受けることがあります。
そこで「必ず稼げる」などの言葉を発していた場合、誇大広告として返金申請が可能です。
特にメールは確実な証拠として利用できるので、スクリーンショットなどで必ず保管するようにしてください。
情報商材の支払いを拒否したい際の相談先4選
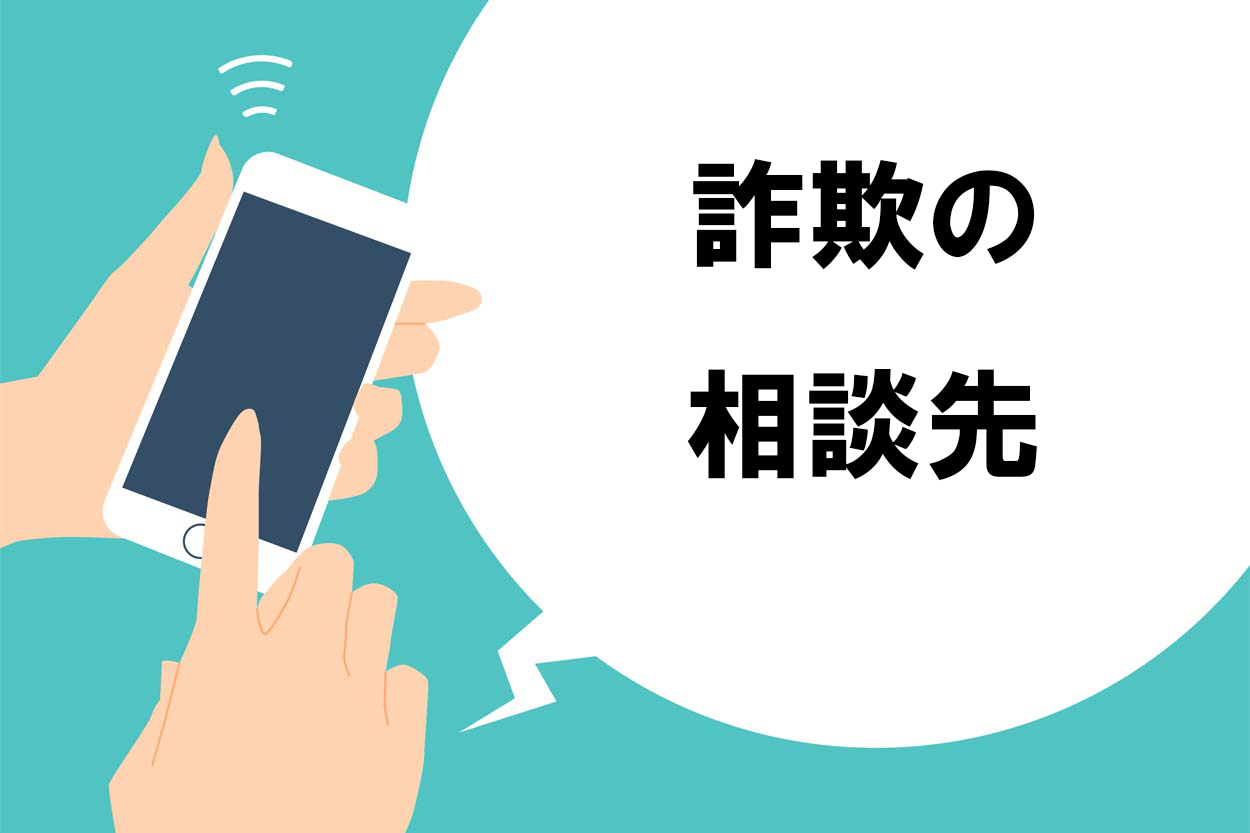
情報商材の支払いの拒否は自分ひとりでも申請することが可能ですが、状況によっては法的な知識が必要になるなど、うまく進まないことも多いです。
そこでこちらでは、情報商材の支払いを拒否したい際の相談先を紹介します。
- 弁護士
- 国民生活センター
- クレジットカード会社
- 警察
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.弁護士
弁護士は金銭トラブルなどを解決してくれる存在として、最も力を発揮してくれる存在です。
被害者に変わって詐欺の証拠を集めたり、返金の請求を代行したりできます。
返金交渉がうまく行かない場合に民事訴訟を起こすなど、法的な知識に基づいて的確な対応をしてくれるのが、弁護士の魅力です。
料金は弁護士によって様々ですが、中には無料で相談できたり、着手金がかからなかったりする事務所も存在します。
情報商材の支払いを拒否したい場合には、まずは無料で相談をしてみることがおすすめです。
2.国民生活センター
「国民生活センター」も、相談先として優秀な施設です。地方自治体が運営しており、無料で相談できます。
国民生活センターでは詐欺被害に関する相談をしたり、状況によっては「ADR(裁判外紛争解決手続)」という方法を取ることも可能です。
ADRを利用すると、法的な強制力を持って、相手との交渉を行えます。
中立な立場で解決策を提示してくれるため、購入者一人で交渉を行うよりも確実に返金の申請を行うことができるでしょう。
3.クレジットカード会社
情報商材をクレジットカードを使用して購入していた場合、チャージバックという制度を利用して、支払いを拒否することが可能です。
チャージバックは、成りすまし被害にあったり、詐欺被害を受けたりした場合に、支払いの処理を取り消してくれるという制度です。
カード会社が支払い処理を取り消してくれるため、お金を支払う必要がありません。
さらにリボや分割払いを使っている場合でも、クレジットカード会社に申請すれば以降の取引を取り消してくれる可能性があります。
チャージバックの申請が通るかどうかは商材の内容や状況によりますが、クレジットカードで決済をした人はまず相談してみると良いでしょう。
4.警察
あまりに悪質な情報商材を購入してしまった場合は、警察に相談することも解決策のひとつです。
警察に被害届けを提出し、取引に違法性が認められた場合は、事業者を逮捕してくれる可能性があります。
ただし警察は、情報商材の購入のように個人と事業者感のトラブル(民事事件)には介入できないため、逮捕されたからといって返金は受けられません。
実際に返金を受けるには、被害者自身が民事訴訟を起こす必要があります。
とはいえ警察が逮捕することで身元が明らかになったり、被害届を取り下げる代わりに返金を要求できたりと、有利に物事を進めることが可能です。
警察に被害届を出しつつ、弁護士に相談することも検討してみてください。
詐欺被害にあった方へ
LINEで無料相談受付中
LINEで無料相談受付中

「なんで騙されてしまったんだ」 「どうにかして返金できないか?」 とお悩みのことでしょう。 実は司法書士に任せると返金される可能性があると知っていましたか? LINEで無料相談できるので、一度返金できるかどうか確認してみてください。
-940x626.png)
-160x160.png)
