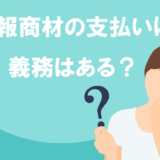「本業とは別に収入を得たい」「新しく何か始めたい」などの理由から、副業を始める人は増えています。
ところが副業を始める人の増加に伴い、詐欺被害の件数も増加しているのが現状です。
特に電話による副業詐欺の被害は多く「電話で勧誘を受けたことがある」「つい信用して商品を買ってしまった」という方もいるのではないでしょうか。
電話による詐欺はインターネット上のものに比べると断りづらいため、被害にあいやすい点が特徴です。
この記事では、電話による副業詐欺の特徴や対処法などを具体的に紹介します。
万が一副業詐欺にあってしまった時の相談先も紹介するので、誤って詐欺商品を購入してしまった方などは、ぜひ記事をご覧ください。
電話における副業詐欺の特徴3選
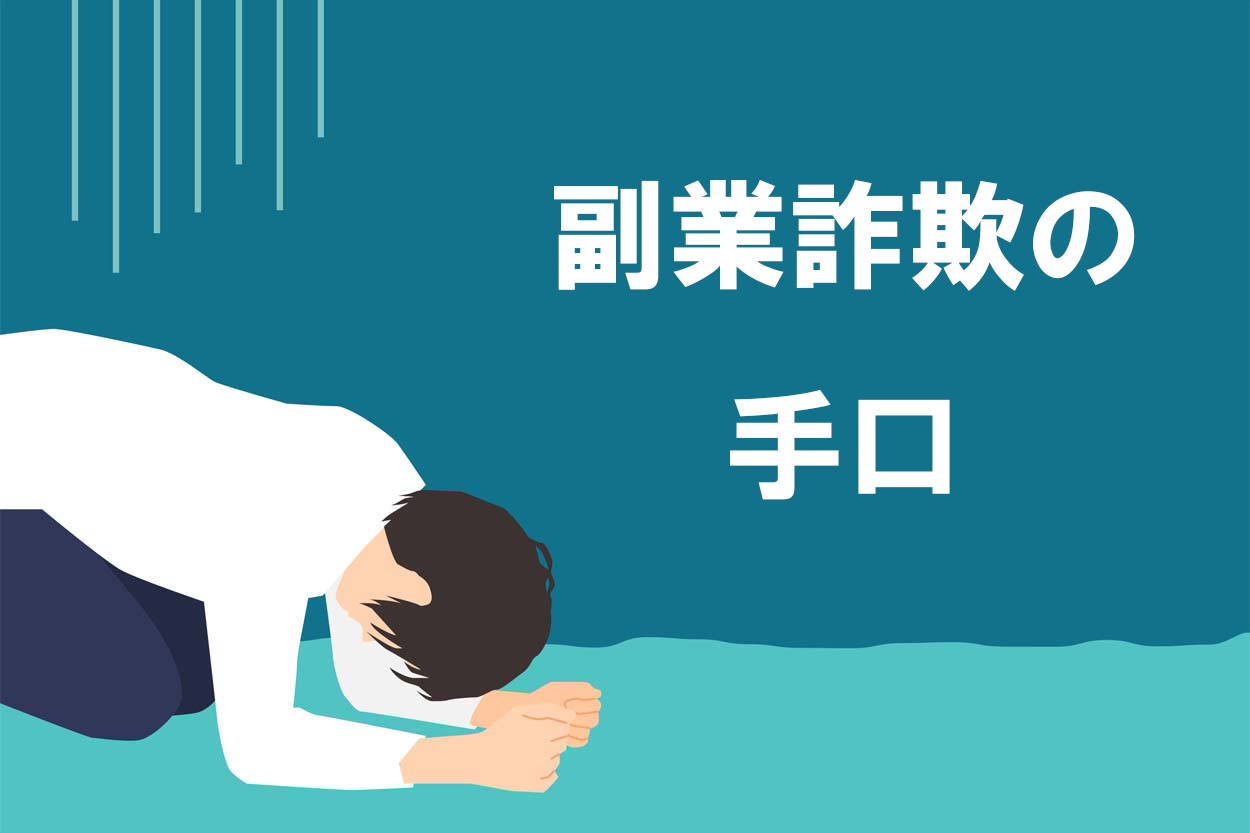
ここでは、電話における副業詐欺の特徴を3つ紹介します。
- 最初は他の名目で電話をかける
- 緊急性を煽る
- しつこく電話をかけてくる
詐欺の電話にはどんな特徴があるのか、それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.最初は他の名目で電話をかける
副業詐欺の電話は「無料相談をしている」など、別の名目で電話をかけて来るケースが多いです。
無料の相談で信用を得て、徐々に悪徳商品の購入に関する話へと発展します。
- 稼げる副業を無料で紹介します
- あなたに合う仕事を分析します
- 国の補助金を使って無料相談を実現しています
などの切り口を用いて、最初は無料で話を進めてから、最終的に詐欺商品を売る手口です。
2.緊急性を煽る
「今始めないと稼げない」「今始めれば誰でも簡単に稼げる」など、電話口で緊急性を煽られる場合は、詐欺の可能性が高いです。
緊急性を煽られると、焦りによって冷静な判断が付かなくなります。
特に通話中は他の人に相談することもできないため、ついつい契約を申し込んでしまいます。
ところが入金後に連絡がつかなくなり、お金と個人情報だけ持っていかれるケースが多いです。
3.しつこく電話をかけてくる
しつこく頻繁に電話をかけてくる場合も、電話における副業詐欺の特徴の1つです。
1度断っても頻繁にかけてくるので疲弊してしまい、最終的に契約へと進んでしまいます。
また感情に訴えることで「これだけ情熱的だから契約してあげよう」と思い、高額商品を購入するケースも後を絶ちません。
電話で副業の勧誘を受けた際の対処法2つ

こちらでは、電話で副業の勧誘を受けた時の対処法を2つ紹介します。
- その場で決めないようにする
- 会話内容を録音する
正しい対処法を理解することで、実際に電話で副業の勧誘を受けた際も冷静に対処できます。それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.その場で決めないようにする
電話口で緊急性を煽る言葉を言われても、その場で契約などはしないようにしましょう。
電話を早く終わらせたいことを優先して正常な判断ができず、悪質な商品を契約してしまうケースが考えられます。
長時間拘束されても、その場で契約せずに一旦電話を切ることが大切です。
また勧誘を断る際は「考えてみます」や「一旦検討します」といった文句は使わないようにしましょう。
相手はまだ見込みがあると感じて、しつこい勧誘につながりかねません。
何度も電話がかかってこないように、相手に情報商材の購入や契約する意思がないことをハッキリ明確に伝えましょう。
2.会話内容を録音する
怪しい電話だと感じた時点で、会話内容を録音しましょう。
会話内容を録音することで「無理やり契約させられた」「脅迫された」など、何か問題が起きた際の証拠として使えます。
また、相手に会話内容を録音する意志を伝えることも有効です。
相手が詐欺師だった場合、会話内容を録音されると詐欺の証拠になるので、録音されることを嫌がります。
会話内容の録音を伝えるだけで、相手が電話を切ることもあります。詐欺の電話だと感じたら、ぜひ試してみてください。
電話での契約はクーリングオフが可能
誤って電話口で商品を契約してしまった場合は、クーリングオフが可能です。
クーリングオフとは、商品の契約に関する書面を受け取った日から、8日以内に販売会社に対して書面で通知することで、契約を無効にできる制度を指します。
さらに相手から契約は取り消せないと嘘をつかれたり、脅してきたりといったケースがある場合、8日を過ぎてもクーリングオフが可能です。
クーリングオフの正しい知識を知っておくと、相手の対応に関係なく冷静に対処でき、契約をスムーズに解除できます。
クーリングオフには書面の通知が必要不可欠なので、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。
万が一副業詐欺にあってしまった際の相談先4選

ここでは、万が一副業被害にあってしまった際の相談先を4つ紹介します。
- 弁護士
- 消費生活センター
- 警察
- クレジットカード会社
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.弁護士
弁護士は副業詐欺を解決するにあたって、最も効果を発揮する相談先です。
詐欺の証拠集めから相手への交渉、民事訴訟などの面倒な業務をすべて代行できます。
「弁護士に相談するとかなりお金がかかりそう」と感じる方もしれませんが、実は無料で相談に乗ってくれる弁護士も存在します。
さらに着手金も無料で、返金に成功した場合に成功報酬を渡すだけでOKという弁護士も多いです。
詐欺にあってしまい返金を希望している方は、まずは弁護士に相談してみてください。
2.消費生活センター
消費生活センターは国や地方自治体が運営している、副業詐欺の電話など悪質な商売の拡大を防ぐための機関です。年末年始を除き、年中無休で対応してくれます。
消費生活相談員が、事業者との交渉方法や具体的な解決策などについてアドバイスをしてくれます。
場合によっては、返金交渉の手伝いも行ってくれるでしょう。
「返金してもらいたいけど、どうしたらいいかわからない」と悩んでいる方は、ぜひ消費者生活センターに連絡してみてください。
3.警察
副業詐欺の被害に関して、警察に頼るのも有効な手段です。
警察の中には「サイバー犯罪相談窓口」という、副業詐欺の被害などを専門に担当する部署があります。
サイバー犯罪相談窓口では、副業詐欺に関する気軽な相談や被害届の提出などが可能です。
被害届を受理した後に、被害内容を見て捜査するかを判断します。状況によっては、詐欺業者の逮捕に繋げられるかもしれません。
ただし、警察は返金に関しては業務の範囲外です。
警察は詐欺行為を行った相手を罰することはできますが、返金までは求められません。
支払った金額の返金まで求める場合は、弁護士にもあわせて相談しましょう。
4.クレジットカード会社
契約にクレジットカードを使用した場合、カード会社に連絡しましょう。
副業詐欺の被害に合った場合、抗弁書という書類を提出できる可能性があります。
抗弁書とは、商品やサービスに明確な問題があることを知らせる書類です。
抗弁書を提出することで、クレジットカードの引き落としを停止できる可能性があります。
また、クレジットカード会社には異議申し立て(チャージバック)制度があります。
異議申し立て制度を利用すると決済を取り消せるので、被害をなかったことにできるでしょう。
詐欺だと認定されればいち早く返金を受けられるため、カード利用者は相談を進めてみてください。