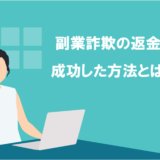近年、副業はじめたいという人をターゲットにした詐欺の被害が増えています。
そこで「どのような副業が詐欺なのか」「自分が始めようとしているものは大丈夫なのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか?
自分が被害にあわないようにするためにも、副業詐欺の特徴は気になるポイントですよね。
そこでこの記事では、副業詐欺の特徴や手口、被害にあわないための対処法などを紹介します。
詐欺被害にあってしまった際の相談先も紹介するので、これから安全に副業を始めたいと考えている方は、ぜひ記事をご覧ください。
副業詐欺の5つの特徴を解説

こちらでは、副業詐欺の特徴を5つ解説します。
- 高額な報酬をうたっている
- 制限時間がついている
- 登録後に料金を請求する
- 業者の素性がわからない
- 「必ず儲かる」などの誇大広告
始めようとしている副業が、詐欺の特徴にあてはまっていないかを確認してみてください。
1.高額な報酬をうたっている
好条件で高額な報酬をうたっている場合は、詐欺の可能性が高いです。
甘い話で消費者の気をひき、最終的に高額商品を売りつけるケースが考えられます。
- 1日10分の作業で月収100万円
- この広告を見た人限定で月50万円稼げる仕事を紹介
など、高額な報酬をうたうキャッチコピーを多用している場合、注意が必要です。
このような副業では、実際に作業をしても高額な報酬は支払われないケースがほとんどです。
酷いものだと「稼げないのはあなたのせいだ」という理由で、高額な商品を購入させる手口も存在します。
2.制限時間がついている
申し込みに制限時間を設定している場合も、詐欺の可能性が高いです。
緊急性をあおり、ユーザーに考える時間を与えないことで、契約へとつなげようと考えています。
- 本日の申し込み限定
- 割引キャンペーンを受けられるのは、後◯時間!
- あと1名だけ募集
上記のように制限時間をつけることで「お得な価格の間に申し込まなければ」と思わせることが目的です。
制限をつけること自体は問題ありませんが、実はずっと表示しているなど、実際に時間制限が無い場合は詐欺にあたります。
3.登録後に料金を請求する
登録の後に料金を請求してくるのも、一般的な副業詐欺の手口です。
最初は無料で勧誘して、申込みが完了した後に金銭を要求してきます。
- 仕事をするには登録料が必要
- 仕事をスムーズに進めるためのツールを先に購入してほしい
- 勉強のために教材を読んでほしい
など、さまざまな方法で料金を請求します。
仕事の開始前に何かと料金を請求してくる副業は、詐欺の可能性が非常に高いです。
4.業者の素性がわからない
募集サイト上に運営企業の情報が記載されていないなど、業者の素性がわからない場合は詐欺のリスクが高いです。
素性を明かさないことで、詐欺行為をした後の追求を逃れようと考えている可能性があります。
- 企業名
- 会社の住所
- 連絡先
- 代表者の氏名
などが明記されていない場合は、怪しいと考えておきましょう。
特にインターネット上で商品を購入する場合、業者には「特定商取引法による表記」の表示義務が課せられています。
「業者の情報が書かれていない=法律違反」であるため、詐欺の可能性が非常に高いと考えておきましょう。
5.「必ず儲かる」などの誇大広告
「必ず儲かる」などの誇大広告を出している副業も、詐欺の可能性が高いです。
報酬や売り上げなど、誰も予想できないものに対して「必ず」「絶対」などの断言する表現は、法律でも禁止されています。
そのため、優良な業者であればこれらの表現は基本使用しません。
それでも「必ず儲かる」という言葉に騙されやすいので、注意が必要です。
副業詐欺にあいやすい人の特徴5選
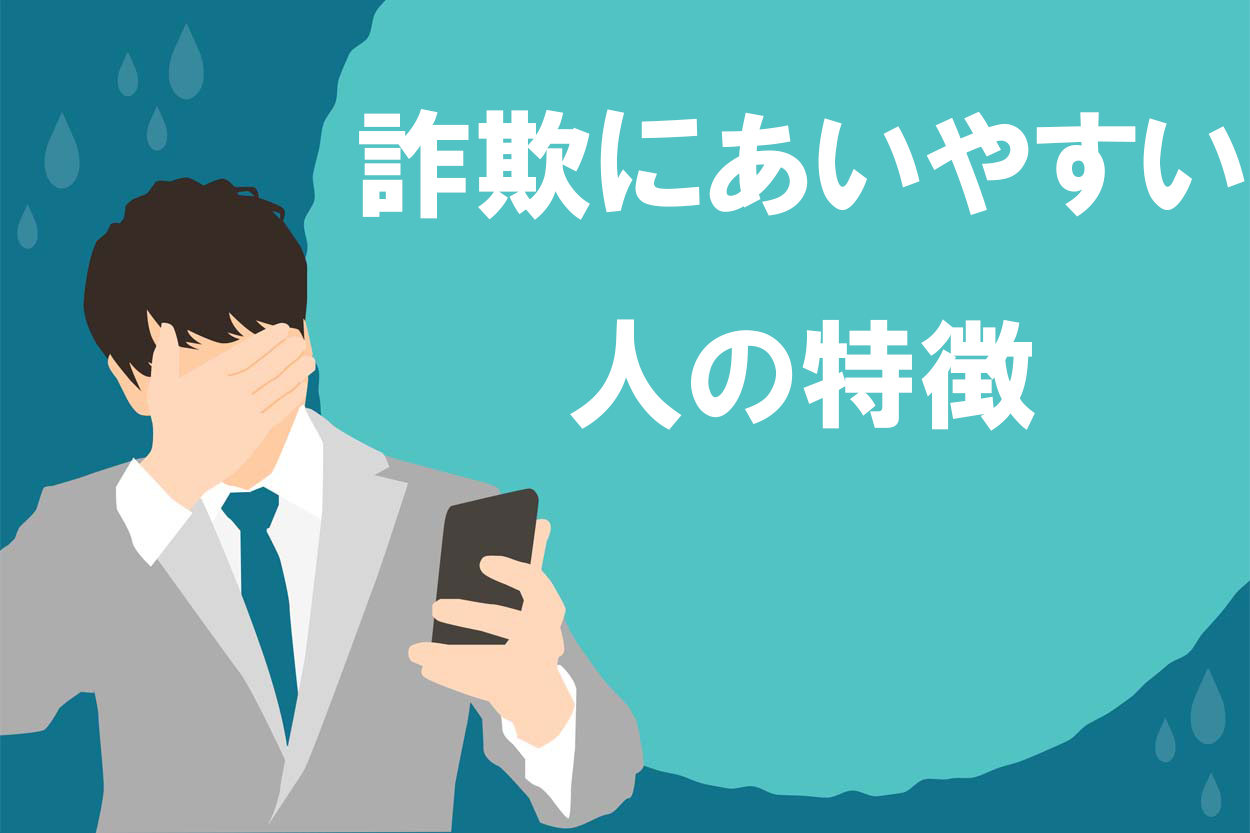
ここでは、副業詐欺にあいやすい人の特徴を5つ紹介します。
- 金欠で焦っている
- よく調べずに登録してしまう
- 人を信じやすい
- 自分に自信がある
- 人に相談しない
それぞれ詳しく確認していきます。
1.金欠で焦っている
金欠で焦りが生じている人は、副業詐欺にかかりやすいといえます。
焦っているため正常な判断ができず、普段なら断っている案件でも登録をリスクが高いです。
実際に金欠と感じる人のIQは、通常の状態に比べて40%も下がるという結果も出ているほど、焦っている状況は判断を狂わせます。
「お金がないから副業をしなければ」という状況に陥っている方は、注意が必要です。
2.よく調べずに登録してしまう
自分でよく調べずにとりあえず登録してしまう方は、詐欺にあう確率が高いです。
例えば「10分で10万円絶対稼げる!」とうたっている副業があるとしましょう。
このようなタイプの副業は口コミなどを調べれば、詐欺かどうかの判断はある程度できます。
ところが何も調べずに登録を進めてしまうと、第三者の意見が無いまま、詐欺師の話が判断の元になってしまいます。
詐欺師は相手を信じ込ませて契約させるプロなので、気がついたときには高額商品を購入していたということにもなりかねません。
よく調べずに勢いで登録を進めてしまう方は、詐欺にあう可能性が高いと考えておきましょう。
3.人を信じやすい
人を信じやすい方も、詐欺被害にあいやすい人の特徴の1つです。
ついつい他人を信じてしまい、詳しい説明を求めたり、質問したりせず、いわれたことを鵜呑みにしやすい傾向にあります。
「この人が言っているから大丈夫だ」という状態は、非常に危険です。
最終的に高額な商材を購入しているということになりかねません。
副業をはじめる際には、人の言葉をすべて鵜呑みにせず、自分でしっかりと考えて判断することが大切です。
4.自分に自信がある
自分に自信がある人ほど、詐欺にあいやすい傾向にあります。
「自分の判断は間違っていない」と思い込んでしまい、詐欺に気づかない可能性が考えられます。
また自信があるため、第三者の意見もあまり聞かない可能性が高いです。
その結果、詐欺への意識が低下して対策を怠り、被害にあいやすくなってしまいます。
5.人に相談しない
他人に相談しない方も、詐欺にあいやすいです。
自分の判断で物事をすすめると、どうしても客観的な目線が少なくなってしまいます。
他の人から見ると明らかにおかしくても、相談しないがゆえに気づけなかったというケースは少なくありません。
副業詐欺の実際の手口を紹介
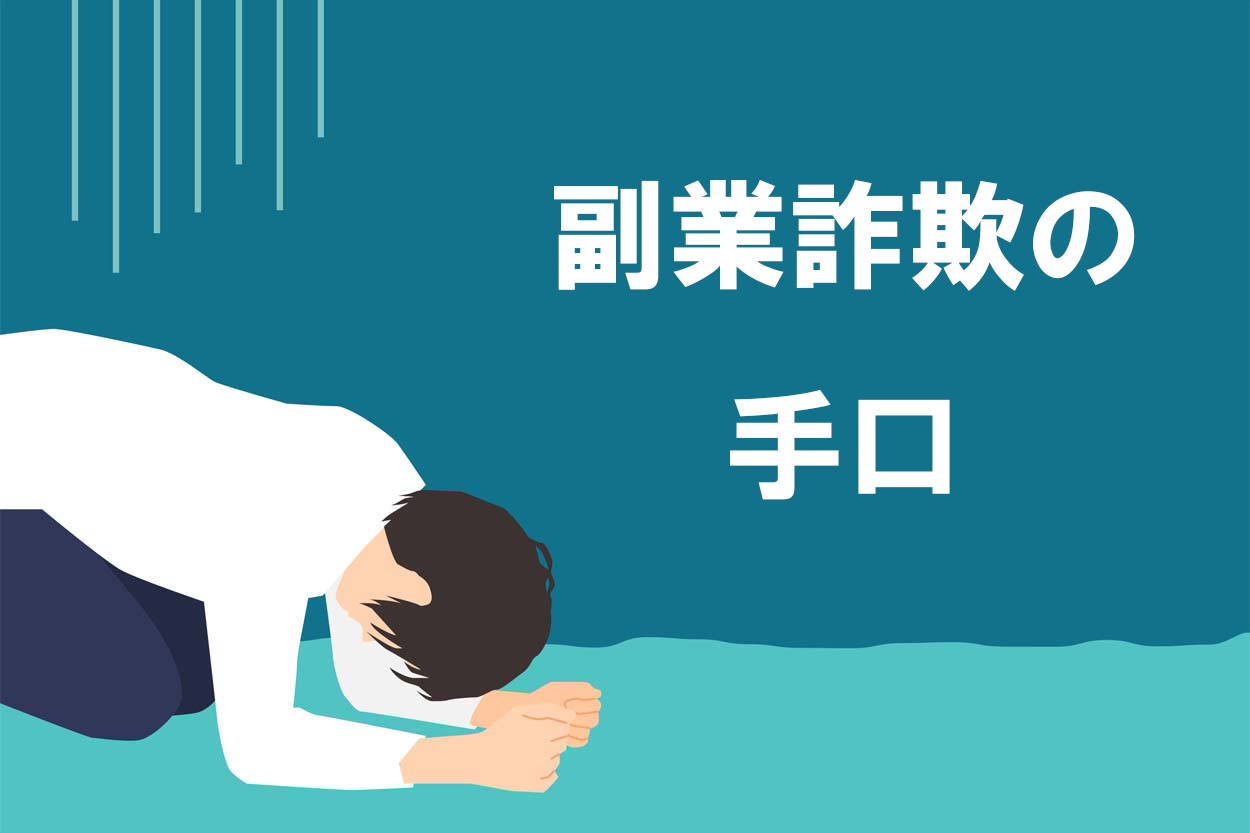
こちらでは、副業詐欺の実際の手口を3つ紹介します。
- 後から高額な情報商材を購入させる
- サイト登録料・保証料を払わせる
- 仕事をはじめる前にお金を払わせようとする
どのような手口があるのか、確認してみてください。
事例1.後から高額な情報商材を購入させる
無料で登録後に高額な情報商材を購入させようとする手口があります。
高額の利益が得られる副業の無料モニターとして登録させて、無料で作業を体験させた後に高額のツール使用料や初期費用の支払いを求めてきます。
この手の方法は詐欺である可能性が非常に高く、絶対に支払わないようにしましょう。
事例2.サイト登録料・保証料を払わせる
副業詐欺の手口として、サイト登録時に登録料や保証料を払わせようとするケースも多いです。「副業をしたい方はこちら!」などのキャッチコピーで誘導し、副業紹介サイトへ登録するための登録料を請求してきます。
近年、サイト内での個人情報交換の保証金として支払いを求めてくる事例もあるようです。このように、登録時に登録料・保証金を請求してくるのは典型的な詐欺といってよいでしょう。
事例3.仕事をはじめる前にお金を払わせようとする
情報商材を購入させるのも副業詐欺の代表的な手口の1つです。「簡単に稼げる」とったキャッチコピーで人を引き付けて、稼げるマニュアルといって情報商材を購入させます。
もちろんマ、ニュアルは詐欺目的の情報商材であるため、商材どおりに作業しても稼ぐことはできません。近年、スマホを持つ未成年が増えたことで、中高生の間でも被害が増えています。
副業詐欺にあわないための3つの対処法
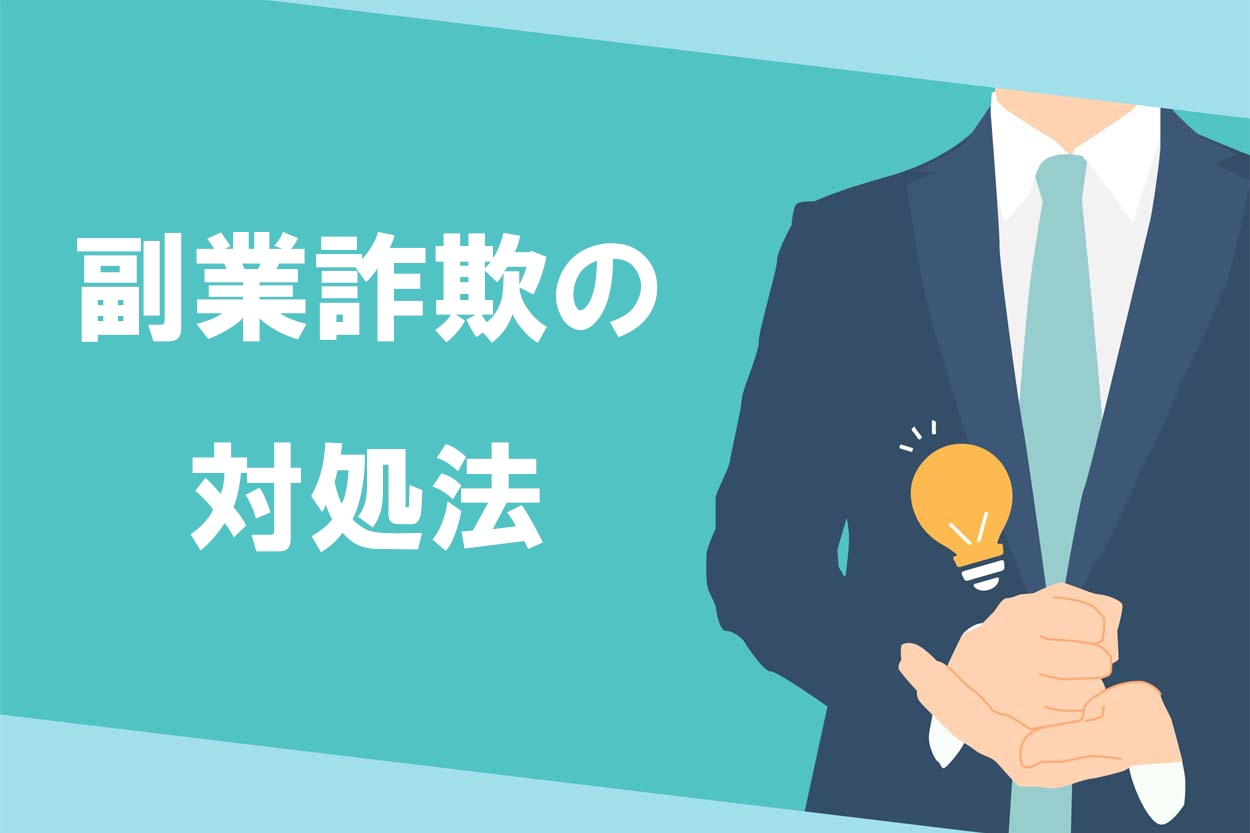
こちらでは、副業詐欺にあわないための対処法を3つ紹介します。
- 先にお金を払わないようにする
- 会社やサービスの口コミを確認する
- 信頼できる機関や人に相談する
どのような対処法があるか、確認してみてください。
1.先にお金を払わないようにする
副業詐欺にあわないためには、始める前にお金を払わないようにしましょう。
資格が必要な仕事を除き、優良業者であれば仕事をはじめる前にお金の支払いを求めることはありません。
- 先にツールの購入が必要
- 副業紹介のための登録料が必要
などの理由で支払いを求められた場合は、詐欺を疑いましょう。
2.会社やサービスの口コミを確認する
詐欺かどうか見極めるには、会社やサービスの口コミを確認してみてください。
現在は副業に関する多くの口コミサイトが存在するため、事前に会社の評判を確認できます。
- 体験談まとめサイト
- Yahoo!知恵袋
- TwitterやFacebookなどのSNS
などで、口コミを確認してから判断しましょう。
3.信頼できる機関や人に相談する
詐欺かどうか不安な方は、家族や親戚、親しい友人など信頼できる相手に相談してみてください。
第三者の客観的な意見を聞くことで、詐欺かどうかの判断がつけやすくなります。
もし親しい人に相談が難しい場合は、国民生活センターなどの公的な機関を利用すると安心です。
国民生活センターであれば、無料で詐欺についての相談が行えます。
自分だけで判断せずに、信頼できる人や機関に相談することを意識しておきましょう。
万が一副業詐欺にあってしまったときの相談先4選

ここでは、万が一副業詐欺にあってしまった場合の相談先を4つ紹介します。
- 弁護士
- 消費生活センター
- 警察
- クレジットカード会社
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.弁護士
副業詐欺にあったときの最適な相談先が弁護士です。
業者への返金請求はもちろん、詐欺調査から訴訟までトータルで代行を行ってくれます。
また、相談料や着手金を無料にしている弁護士も多いです。
返金されたお金の中から費用を支払う仕組みのため、費用負担を抑えられます。
副業詐欺を解決したい場合は、まず弁護士への相談を検討してみてください。
2.消費生活センター
消費生活センターは無料で詐欺被害の相談ができ、必要に応じてアドバイスをしてくれます。
状況次第では、代行して業者へ連絡してくれたり、ADR(裁判外紛争解決手続)を紹介してくれたりと、トラブル解決につながるケースも多いです。
ただし返金請求や訴訟の手続きは代行できないため、確実にお金を取り戻したいのであれば、弁護士にも合わせて相談しておくと良いでしょう。
3.警察
警察に相談してみることも、1つの手段です。
内容が悪質かつ詐欺の可能性が高ければ、逮捕につながるかもしれません。
逮捕されると、裁判の判決次第では業者に刑事罰が課せられます。
そのため刑事罰を恐れて、業者から示談交渉ならびに返金を申し出てくるケースも少なくありません。
ただし返金を要求することは警察の管轄外なので、個人的にお金を取り戻したいのであれば、弁護士などを通じて民事訴訟を起こしましょう。
4.クレジットカード会社
クレジットカード会社へ相談すれば、チャージバック(決済取り消し)制度によって決済をキャンセルできるかもしれません。
キャンセルが認められると、支払った分のお金が戻ってきます。
分割払いやリボ払いの場合でも、悪質な詐欺に利用されている場合は、チャージバックが適用可能です。
ただし適用条件はカードによって異なるため、まずはクレジットカードの運営会社に問い合わせてみてください。
詐欺被害にあった方へ
LINEで無料相談受付中
LINEで無料相談受付中

「なんで騙されてしまったんだ」 「どうにかして返金できないか?」 とお悩みのことでしょう。 実は司法書士に任せると返金される可能性があると知っていましたか? LINEで無料相談できるので、一度返金できるかどうか確認してみてください。