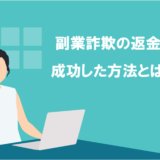昨今の副業ブームにともなって、多くの情報商材を見かけるようになりました。
ところが優良な情報商材ばかりでなく、稼ぎたいという心理に漬け込んで詐欺を働く業者が多いのが現状です。
情報商材が詐欺かどうか見極めるポイントのひとつが「特定商取引法を守って商材を販売しているかどうか」です。
ところがどのような法律かがわからないと、いまいち信頼できるかどうかを見極めづらいですよね、
そこでこの記事では、特定商取引法の概要や、法律に違反している情報商材詐欺の具体例について解説します。
購入した情報商材が特定商取引法に違反している場合の対処法についても紹介するので、情報商材の購入を検討している方は、ぜひ記事をご覧ください。
そもそも特定商取引法とは?サクッと30秒で解説
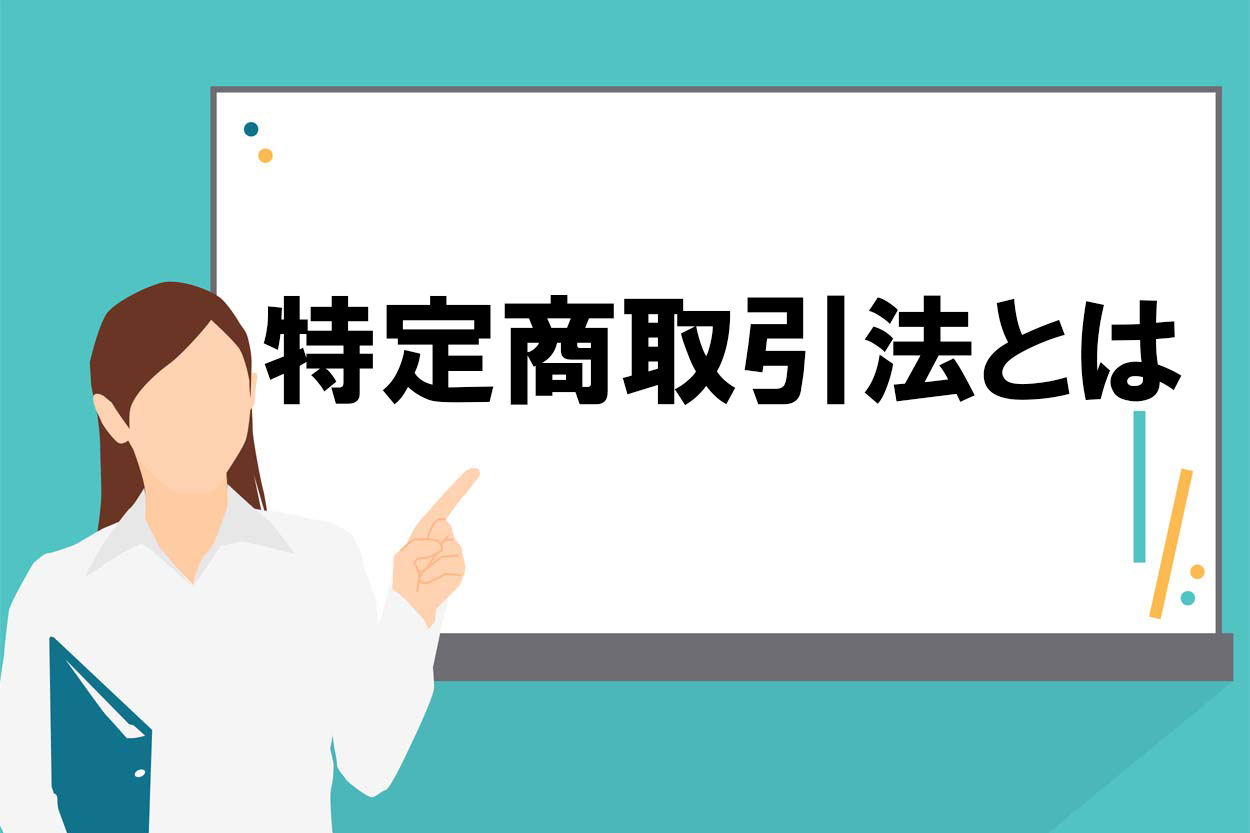
そもそも特定商取引法とはどのようなものなのか、こちらでは詳しい内容を解説していきます。
- 概要
- 規制内容
- 対象となる取引
詐欺の被害にあわないためにも、しっかりと内容を理解しておきましょう。
概要
特定商取引法とは、消費者トラブルが起きやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールを定めている法律です。
業者にルールを設けることで悪質な販売行為を防止し、通信販売や訪問販売などを利用する消費者を守ります。
ネット販売されている情報商材は「通信販売」に該当するため、特定商取引法の対象です。
よって、情報商材を販売する業者は特定商取引法に定められたルールを守らなければなりません。
規制内容
特定商取引法の規制内容について確認していきます。
規制対象となる一例は次のとおりです。
- 商品価格が市場価格や商品価値よりも異常に高額
- 勧誘時の内容と商品内容が異なる
- 証拠を残す契約方法を実践していない
- 誇大広告を行っている
- 事実隠ぺいなどの不適切な勧誘
- 広告に商品価格や販売業者名などが表示されていない
- 承諾していない人への電子メール送信
上記の規制内容を守っていない情報商材は特定商取引法違反となるため、詐欺の可能性が高いといえます。
対象となる取引
特定商取引の対象となる取引は以下のとおりです。
- 通信販売
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 訪問購入
- 連鎖販売取引
- 業務提供誘引販売取引
- 特定継続的役務提供
仮に情報商材をネットで購入した場合は「通信販売」に該当します。
特定商取引法のルールに沿っていない場合は、情報商材詐欺の可能性が高いと判断しましょう。
特定商取引法に基づく表記に書くべき内容7つ
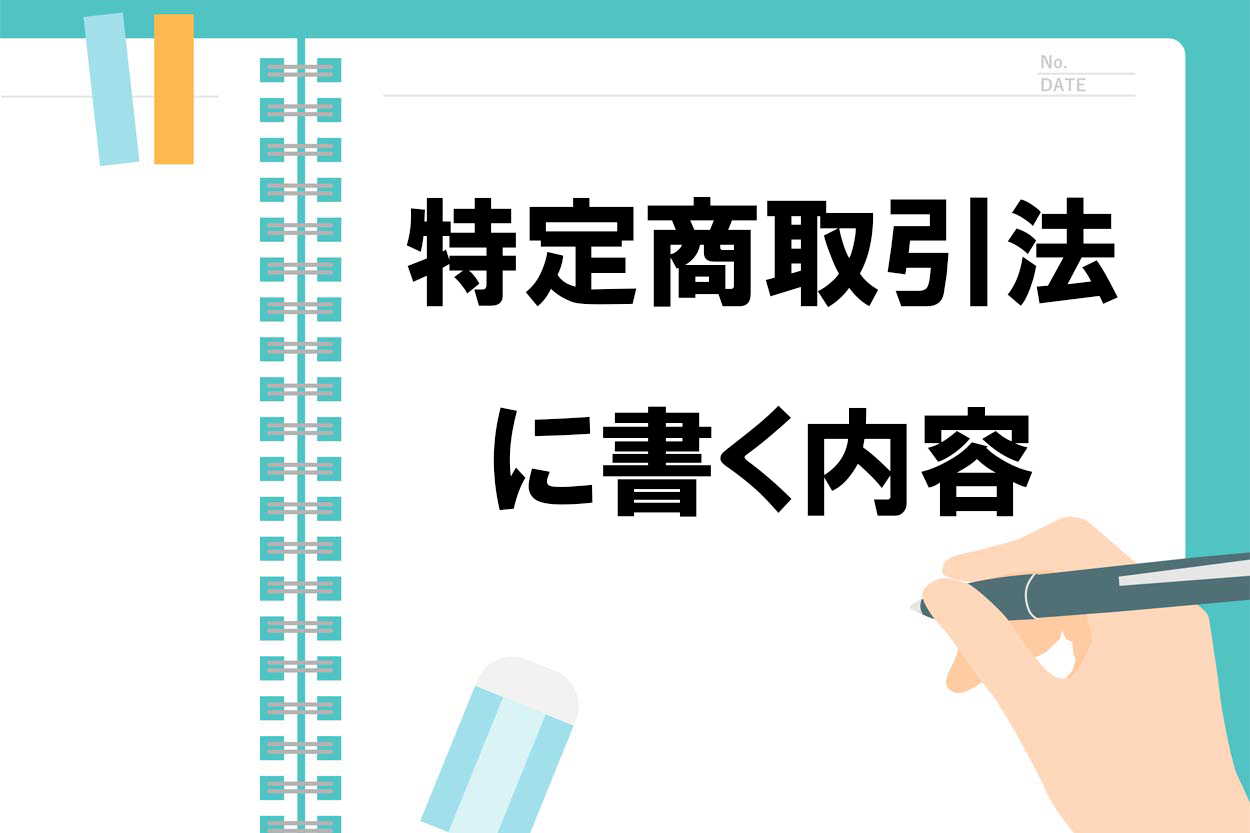
特定商取引法に基づく表記を書くべき内容は、以下の7つです。怪しい情報商材を見抜くためにも、内容を理解しておきましょう。
- 商品価格(税込表記)
- 送料や振込手数料などの購入付帯費用
- 商品の引き渡し日
- 代金支払い方法や支払い時期
- 返品条件・不良品や破損時の対応
- 運営業者の基本情報(業者名・住所・連絡先・営業時間・休業日など)
- 販売量の制限や販売条件がある場合はそれらも記載
これらの情報は消費者にとって重要事項であるため、書かれていない状態で商品を販売することは、特定商取引法の違反行為です。
特に運営業者の基本情報は、詐欺やトラブルに巻き込まれた場合の連絡手段として欠かせません。
販売業者や情報商材の内容が不明瞭な場合は、詐欺の可能性が高いです。
特定商取引法に違反している情報商材詐欺の例5選
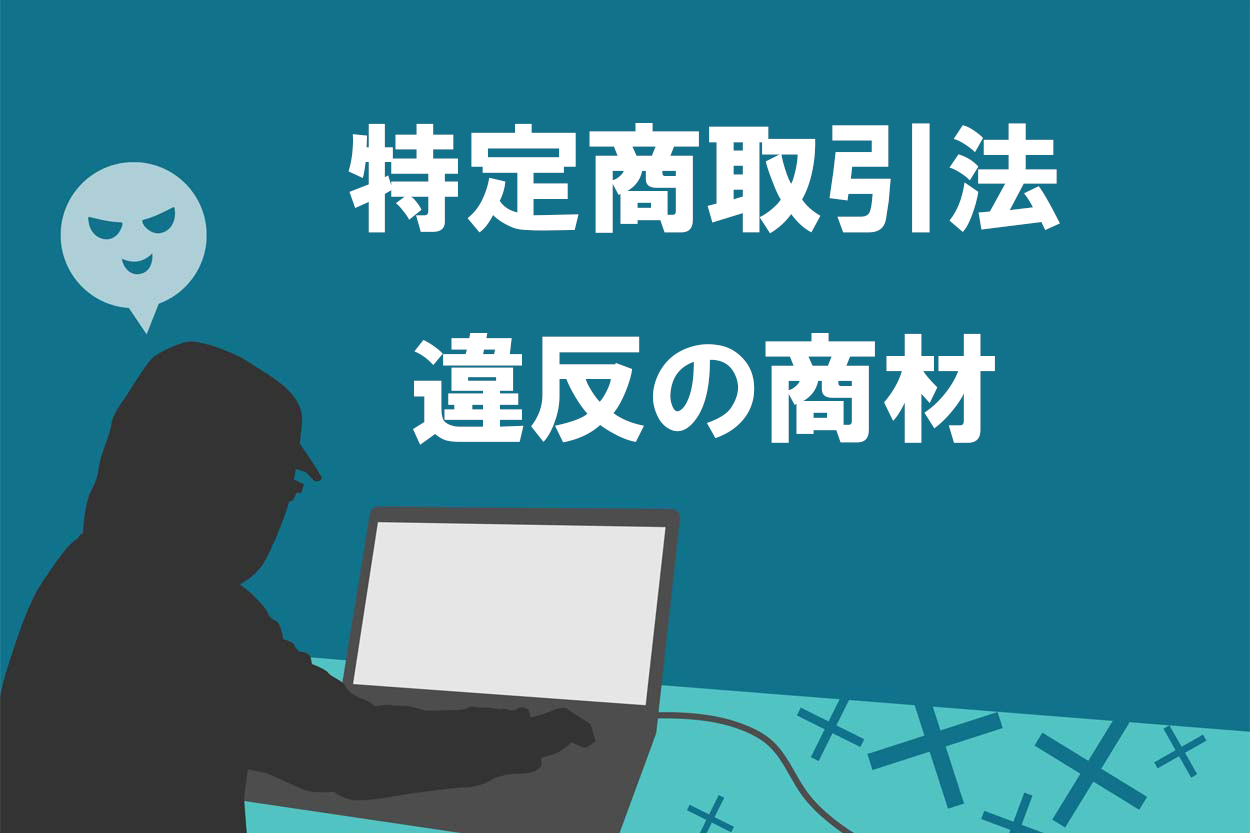
こちらでは、特定商取引法に違反している情報商材詐欺の例を5つ紹介します。
- 特定商取引法に基づく表記がない
- 広告に嘘が使われている
- 不適切な勧誘方法をとっている
- 重要事項の不告知
- 勧誘目的を伏せている
購入しようとしている情報商材が、特定商取引に違反していないかを確認してみてください。
1.特定商取引法に基づく表記がない
特定商取引法に基づく表記がない場合は違法であり、情報商材詐欺の可能性が高いです。
また、特定商取引法に基づく表記はわかりやすい内容で、ユーザーが見つけやすい場所に掲載する必要があります。
また記載のポイントとして、次の2つの項目も押さえておかなければなりません。
- 特定商取引法に基づく表記の専用ページを設ける
- 商品購入・トップページに定商取引法に基づく表記ページへのリンク設定
特定商取引法に基づく表記があっても、わかりにくい内容や見つけにくい場所に記載されている場合は、意図的に隠している可能性があります。
2.広告に嘘が使われている
広告に嘘が使われていて、実物とは内容が異なる場合もあります。
例えば「稼げる情報商材が無料!」などとうたっていながら、実際は無料ではないなどのケースも、情報商材詐欺の手口です。
- 1日5分で必ず稼げる
- 誰でも月収100万円
- 何もしなくてOK
このように、広告に嘘が使われている場合は「虚偽広告」に該当するため、お金を請求されても支払わないようにしましょう。
3.不適切な勧誘方法をとっている
断っているにもかからず何度も勧誘してきたり、なにかと理由をつけて解約の申し出に応じなったりといった対応をとる業者もあります。
このような不適切な勧誘方法をとっている場合も、情報商材詐欺の可能性が高いです。
必要以上にしつこく勧誘してくる場合は、詐欺を疑うようにしてください。
4.重要事項の不告知
事業事項を告知していないものも、悪質な情報商材詐欺の特徴です。
例えば、取引契約をすると毎月1万円の商品を継続購入しなければならないとします。
ところが消費者に対して「とりあえず1万円払えばOKです」と、継続購入だということを伏せている場合は、違反行為に該当します。
このように重要な条件を告知せずに契約させ、お金を支払わせようとするのも情報商材詐欺によくある手口です。
これらの手口は「金銭をともなう重要事項の不告知」に該当し、規制対象となります。
5.勧誘目的を伏せている
勧誘目的を伏せて近づいてくる業者も、特定商取引法に違反している可能性が高いです。
勧誘行為を行う場合は、企業名や目的を伝えた上で行わなくてはなりません。
代表的な例が「ネットワークビジネス」です。
世間の評判がよくないことから「ホームパーティーがあるから来ない?」などと、内容を伏せた状態で勧誘行為を行うケースが多発しています。
本来の目的を伏せた勧誘は、原則として法律違反だということを覚えておきましょう。
購入した情報商材が特定商取引法に違反している際の対処法

ここでは、購入した情報商材が特定商取引法に違反している場合の対処法を5つ解説します。
- 弁護士に相談する
- クーリングオフを適用する
- 消費生活センターに相談する
- クレジットカードのチャージバックを利用する
- 警察に相談する
それぞれの内容について、詳しく解説します。
1.弁護士に相談する
購入した情報商材が特定商取引法に違反している際は、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、被害者に代行して和解・返金交渉を行ってくれます。
あまりにも業者が悪質な場合は、詐欺の調査から告訴までを代行してくれるため、トラブルの解決につながりやすいです。
相談料や着手金が無料の弁護士であれば、追加でお金の負担が発生することもありません。
業者に連絡しても、返金や解約の対応をしてくれない場合には、まず弁護士への相談を検討してみてください。
2.クーリングオフを適用する
特定商取引法に定められているクーリングオフ制度を一定期間内に適用することで、無条件で契約解除や返金が可能です。
クーリングオフ制度は取引内容によって適用期間が異なるため、該当するかどうかを確認しておきましょう。
ただしインターネットで商品を購入した場合は、クーリングオフの対象取引に該当しません。
「自らの意志で商品を購入した」と捉えられるからです。
情報商材はインターネットからの購入がメインですが、電話等で追加の勧誘を受けるなどした場合は、クーリングオフを適用できる可能性があります。
3.消費生活センターに相談する
消費生活センターに相談してみるのも有効な対処法の1つです。
消費者ホットライン「188」に連絡すると、情報商材トラブルの相談ができ、専門相談員による無料アドバイスを受けられます。
状況に応じて、業者との交渉のフォローや弁護士や関係する団体なども紹介してくれるため、対処法が分からない場合は最初に連絡するとよいでしょう。
4.クレジットカードのチャージバックを利用する
情報商材をクレジットカードで購入した場合、チャージバックを利用することで、支払いの取り消しと返金が行える可能性があります。
チャージバックとは、クレジットカードが定めている制度で、適用が認められると決済が取り消されて返金される制度です。
適用条件はカード会社によって異なるため、制度の利用可否はカード会社に問い合わせてみてください。
5.警察に相談する
業者が悪質で詐欺だと判明しているにもかかわらず、一切対応しない場合は警察に相談するとよいでしょう。
警察が悪質だと判断した場合は、詐欺罪などの罪に問うことができます。
刑事罰を科せられると今後の運営に影響することから、業者から示談と返金を申し出るケースも少なくありません。
ただし、刑事告訴する場合は弁護士のサポートが必要となるので、並行して弁護士へ相談しておくとよいでしょう。