年金制度の破綻や、企業の終身雇用打ち辞めなど、自分の力でお金を稼がなくてはならない時代へと突入しつつあります。
そこで少しでも収入を増やすために副業を始めようと考えているものの、詐欺が怖くてなかなか一歩踏み出せないという方もいるのではないでしょうか?
副業に関するトラブルを見ていると、不安が大きくなりますよね。
この記事では、副業詐欺で実際によくある手口や、引っかかってしまう方の特徴について紹介します。
これから副業を始めようと思っている方や詐欺に関して知りたい方はぜひ記事をご覧ください。
副業詐欺で多い手口を5つの事例で解説
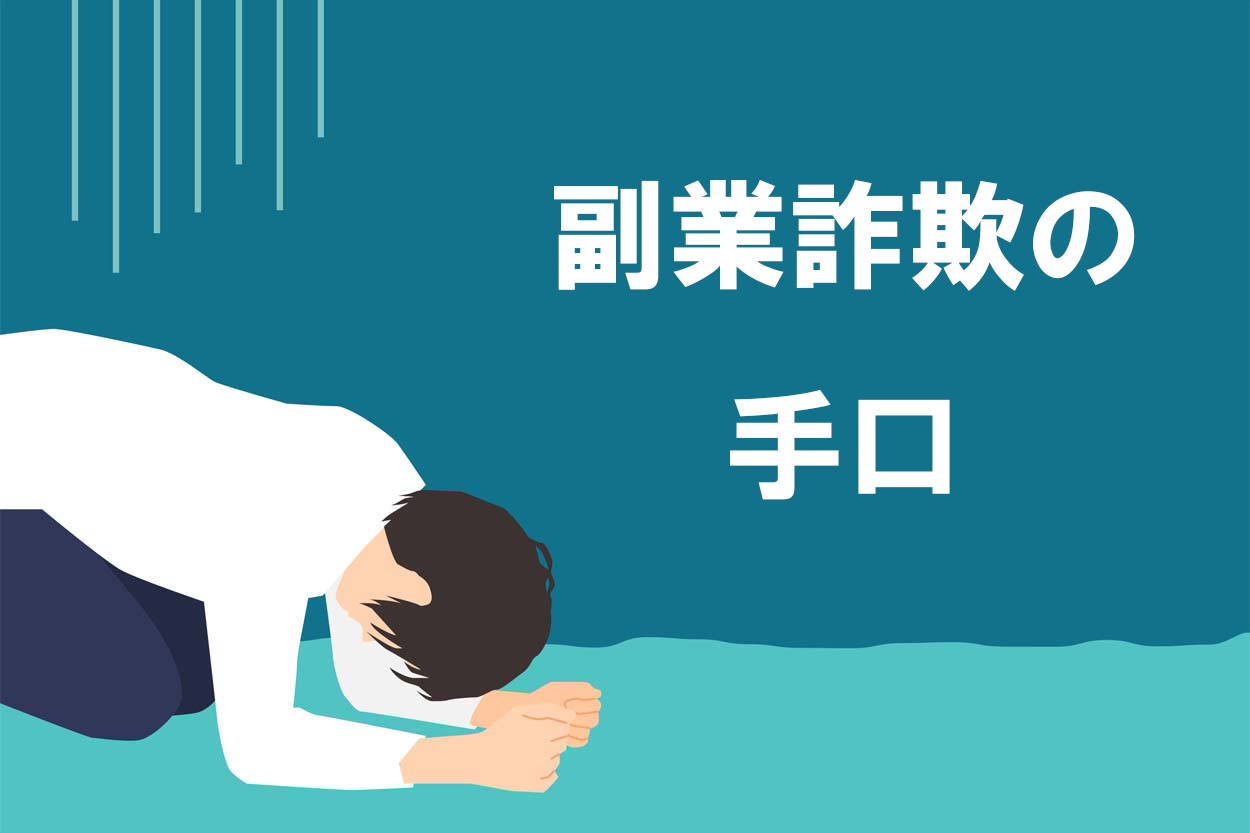
こちらでは、副業詐欺で多い手口を5つ紹介します。
- セミナーやスクールを年間払い
- 商品を購入させる
- コンサル料金を支払わせる
- 仕事を紹介するための入会金を徴収する仕事をしても報酬を振り込まない
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.セミナーやスクールを年間払い
副業詐欺でよくあるのが「ビジネスについて先に学ぶ必要がある」といい、その受講費を請求するというやり方です。
セミナーに大金を払って受講しても中身は薄く、ほぼ稼げるようにはなりません。
最初から高額なスクールに入会させるわけではなく、はじめは無料で数時間のセミナーに参加ができることが多いです。
その1回目のセミナーで言葉巧みに、副業の良さや参加者の成功例をあげます。
サクラなどを用いて「入ったほうがいい」「自分でもできるかもしれない」と思わせて、最終的に高額なセミナーへと入会を促します。
2.商品を購入させる
仕事を始める前に「最初にこの商品を買う必要があるけど、最終的に取り返せる」といって、高額な商品を購入させる手口です。
ユーザーは「後で取り返せるなら……」と高額な支払いを進めますが、実際には稼げなかったり、業者と連絡が取れなくなったりして、詐欺と判明します。
この副業詐欺で購入を強制される商品の例は、主に以下のとおりです。
- せどりで使用するための自動ツール
- FXで必勝できるシステムが入ったUSB
- ネットショップ運営に必要なパソコン
- ビジネスを始めるための教材
「後で取り返せる」と言うことで心理的なハードルを下げる、悪質な手口です。
3.コンサル料金を支払わせる
業界では、その業種で成果を上げ実績のある人が、初心者や中級者に対してコンサルティングをするという手法がよく行われています。
コンサルティング自体は詐欺行為ではありませんが、中には自分自身の実績を偽装して、中身のないようなコンサルをしている人も多いのが現状です。
主な手口としては、まず無料セミナーを開き、簡単にビジネスについて触れたあとに「本気で稼ぎたい人はコンサルを受けてください」といった形で募集します。
仮に稼げない人がいても、購入者的には「自分の実力不足だ」「努力が足りない」などの心理的な思いが強くなり、被害にあっていると気づきません。
中には優良なコンサルもあるため、嘘がわかりにくい点が、副業コンサル詐欺の実態です。
4.仕事を紹介するための入会金を徴収する
副業を紹介するために、サイトやサービスへの入会金を徴収するケースです。
「高額な副業を紹介する会員専門サイト」などの触れ込みで、数万円~数十万円の会費を請求します。
購入者的にはこちらも「最終的には副業で取り返せる」という思いから、ついつい登録を進めてしまうのです。
実際には副業が紹介されず、業者に問い合わせても返事がなかったり、話をはぐらかされたりしてしまいます。
悪質なサイトでは月額プランによって、長くお金を奪うこともあるなど、悪質な手口です。
5.仕事をしても報酬を振り込まない
「1日にたった数分アンケートを受けるだけで1万円!」というような宣伝は、注意が必要な手口です。
このような手口では実際に仕事をしても報酬が振り込まれなかったり、手数料を支払わないと出金ができなかったりと、結局お金を受け取れないケースが多発しています。
仕方なく手数料を振り込んでも、結局あらかじめ言われていた額の報酬が振り込まれずに、そのまま逃げられてしまうケースが後を絶ちません。
副業詐欺の勧誘場所3選
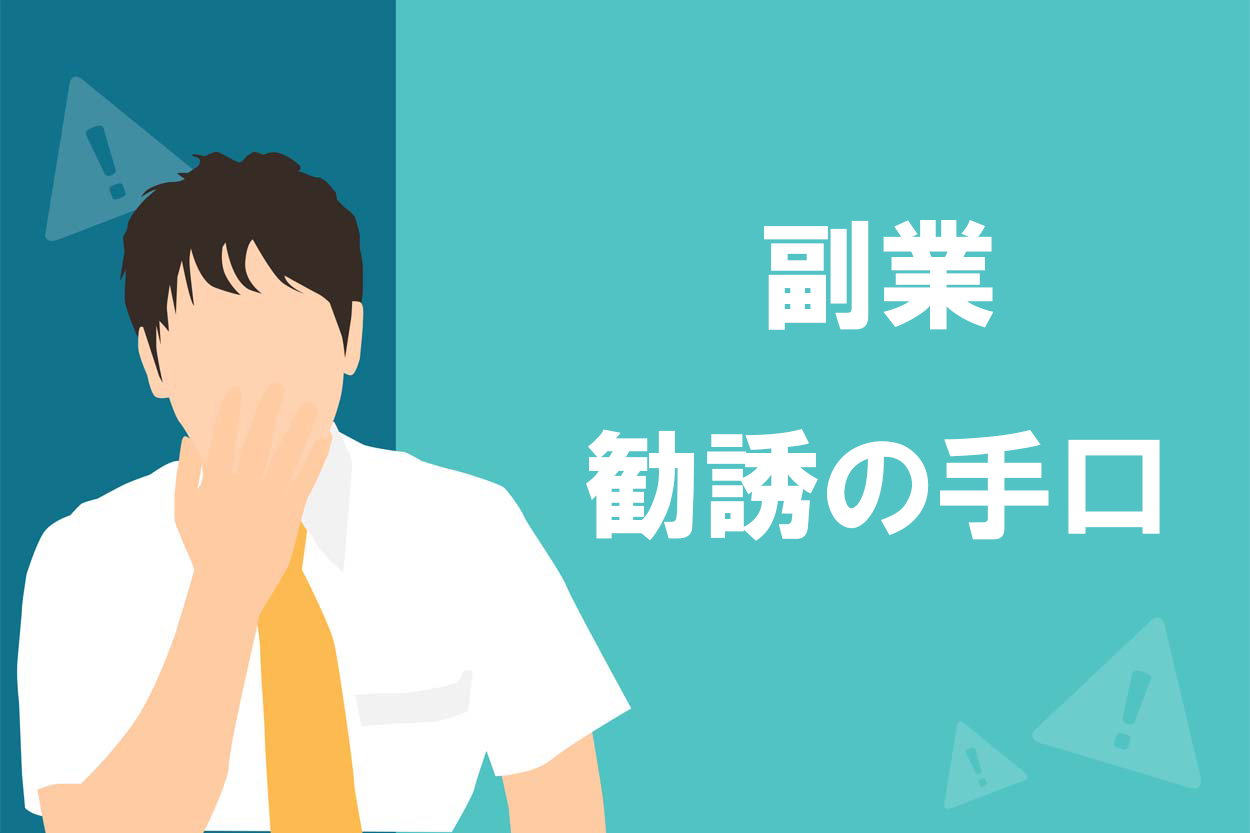
こちらでは、副業詐欺でよくある勧誘の手口を3つ紹介します。
- SNS
- インターネット広告
- 知人の紹介
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.SNS
ネットの発達とスマホの普及により年々増加傾向にあるのが、SNSを介した詐欺です。
SNSで「これだけ稼げました!」というアピールに興味を持ったユーザーを、無料のLINEに登録して商材を販売します。
他には「ギフト券◯万円分プレゼント」という企画を行い、個人情報を入手して別の業者に売るなど、悪質な手口が多いです。
特に大多数が利用しているTwitterやInstagramといった人気のSNSは、副業ビジネスの宝庫。
主に「お金がない」「副業を始めたい」と発信しているユーザーに、ダイレクトメッセージなどを利用して話しかけます。
2.インターネット広告
インターネット上に表示される広告の中でも、詐欺が行われていることがあります。
「スマホだけで楽に副収入」「誰でもできる簡単な仕事」などの謳い文句で、勧誘を行います。
広告をクリックした先には詳しい情報が載っておらず、メールマガジンやLINEに登録したユーザーを狙って、商品を販売するケースです。
YouTubeやTwitterなど、多くの人の目に留まりやすい場所に広告を出稿しています。
3.知人の紹介
意外と多いのが知人から紹介され、被害額が出て悩んでいるというパターンです。
知り合いや友人から商品を買うよう促されたり、怪しい副業を勧められて断れずにはじめてしまう人は一定数います。
「紹介してくる側も騙されていることに気づいていない」ということも稀にありますが、大半は紹介料を得るために話を持ちかけてくるケースが多いです。
面識のある知人や友人に話を持ちかけられると詐欺だと気付きにくく、断りにくいことから被害にあってしまいます。
副業詐欺に騙されやすい人の特徴4つ
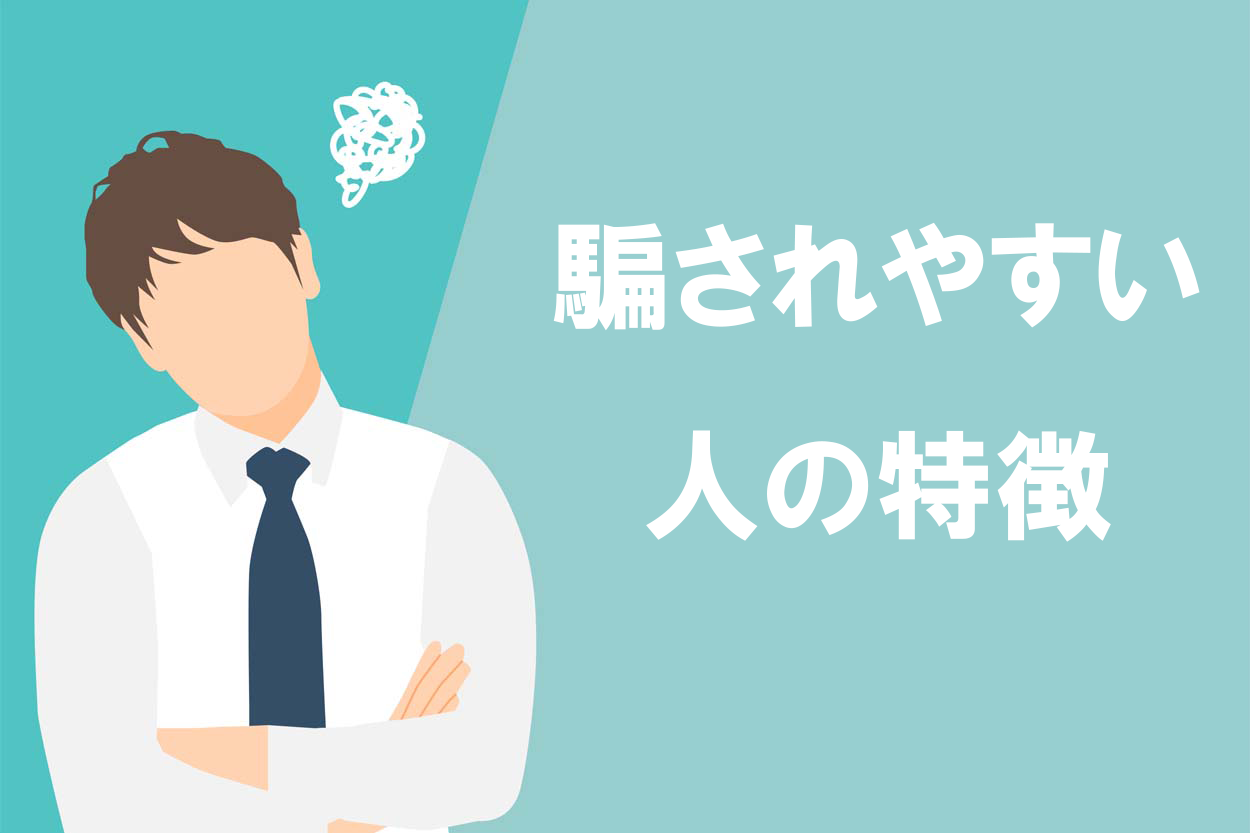
こちらでは、副業詐欺に騙されやすい人の特徴を4つ紹介します。
- お金がなくて焦っている
- よく調べない
- 人を信じやすい
- 自分は騙されないと思っている
それぞれ確認して、自衛する意識を持ってみてください。
1.お金がなくて焦っている
副業詐欺に遭ってしまう人に絶対的に共通しているのが「お金に困っている」という点です。
お金に困っているあまり、正常な判断ができず、詐欺に気づかないまま商品を購入してしまいます。
心理学の研究によると、金欠と感じることでIQテストの結果が40%も下がるという結果があるようです。
- 現状の仕事に不満を感じている
- 収入が少ない
- 借金がある
など、生活に不満を抱えている人ほど、詐欺に引っかかりやすい傾向にあります。
2.よく調べない
自分でしっかりリサーチせず、深く考えずにとりあえずやってしまう人は、詐欺に遭いやすい傾向にあります。
運営会社や実際の口コミなど、調べることで商品の内容はある程度判明します。ところが詐欺師の巧妙な話術や文章によって「とりあえずやってみようかな」と調べる時間を与えずに契約させるケースが多いです。
「今を逃すとチャンスがない」「あと◯時間で募集が完了する」などの、時間を使った勧誘には気をつけたほうが良いでしょう。
勢いで行動してしまうことが多い人には、注意が必要です。
3.人を信じやすい
ネットの世界では、自分でも気づかないうちにマインドコントロールされていることがあります。
SNSでインフルエンサーの発信を見ているうちにファンになってしまい、商材へ何十万もお金を注いで、はじめて詐欺だったと気づくケースが存在します。
- セミナーで数時間話を聞くだけで信頼する
- 優しい発信に好感を覚える
- カウンセリングなどで親身に話を聞いてくれる
などに覚えがある方は、詐欺に引っかかる可能性が高いです。
4.自分は騙されないと思っている
実際に詐欺被害に遭った人の多くが「まさか自分がこんな目にあうとは思わなかった」というような発言をします。
詐欺なんて普通にしていればあわないだろうという慢心は、決して自分の身を守ることにはなりません。
副業は雇用形態が不安定なものが多いので、何かトラブルがあった際には自分で解決する必要が生じてくるかもしれません。
「もし騙されたらどうするか」を考えて頭の中を整理しておくだけでも、被害への予防になるでしょう。
万が一副業詐欺にあってしまった場合の相談先3選

こちらでは万が一、副業詐欺にあってしまった場合の相談先を3つ紹介します。
- 弁護士
- 消費者センター
- 警察
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.弁護士
詐欺被害に遭った場合に最も有効な手段は、弁護士に相談・依頼をするという方法です。
インターネットを介した被害は、相手の身元が不明であることが多く個人での解決は非常に難しいのが実情です。
さらに副業詐欺の場合は、相手との交渉や和解ができない事例が大多数を占めています。
時間ばかりが過ぎてしまい、結局泣き寝入りしてしまう人が多いのです。
法律のプロである弁護士に相談すれば、法的な根拠に基づいた解決のための手段が取れるので、無事返金されることも十分にありえます。
実際に100万円以上のお金を取り返したケースもあるなど、実績は豊富です。
無料で相談できる弁護士も多いため、まずはプロに問い合わせてみることをおすすめします。
副業詐欺の返金に強い弁護士は「副業詐欺の返金に強い弁護士の選び方」の記事にて詳しく説明しています。
2.消費者センター
消費生活センターに電話で直接相談してみるのもひとつの手段です。
詐欺被害に関する相談に、無料で対応してくれます。
ネットでの消費者問題は、このような第三者的機関を間に挟むことで比較的容易に解決しやすくなります。
また似たようなトラブル事例がホームページに掲載されていることもあるので見てみると参考になるかもしれません。
ただし原則は「相談のみ」で、本気でお金を取り返そうと思うなら、別で弁護士などを立てたほうがスムーズに進む可能性が高いです。
3.警察
実際に金銭のやりとりがあった・多額の支払いをしてしまった際には、警察相談専用電話(#9110)に電話してみるのも良いでしょう。
悪質商法に対する具体的な対策の提案や、被害届を提出することで相手の犯罪抑止になる可能性があります。
ですが被害届を出すと必ず捜査してくれるとは限りません。
また警察ができるのは犯罪者の逮捕や懲罰なので、被害者に対する返金は個人が訴訟を起こす必要があります。
直接的な返金につながるとは限らないので、あくまでも相談先の1つとして考えておくのが無難です。
詐欺被害にあった方へ
LINEで無料相談受付中
LINEで無料相談受付中

「なんで騙されてしまったんだ」 「どうにかして返金できないか?」 とお悩みのことでしょう。 実は司法書士に任せると返金される可能性があると知っていましたか? LINEで無料相談できるので、一度返金できるかどうか確認してみてください。
-940x626.png)
-160x160.png)
-160x160.png)